
二度目の邂逅
五百蔵家の庭で、しんらと男は小さな酒宴を開いていた。 結局、廉子の予想通り「妙なやつ」はしんらに文を送っていた蟲師のギンコという青年だった。 ギンコの口が上手いのか、しんらの口が軽いのか、十中八九後者の方が原因で、廉子の言いつけも空しく 果実酒を注いだ器を傾けつつ、左手の事も、蟲を見る性質を持つことも話してしまったのである。 ここで初めて、愛しく思っていたそれらが蟲という名前を持つのを、しんらは知った。 やはりそれが、見えない者にとっては受け入れられないものである、ということも。 「そう、か……」 ギンコの話を聞き、少しだけ寂しそうに顔を傾けたが、同時に今、共に暮らす人の存在の暖かさを確認して しんらの沈んだ顔に、穏やかな笑みが混じる。 理由を知らないギンコは、その表情に腑に落ちないものを感じたが、静かに納得をしたしんらに何も聞かない事にした。 「ところで、しんら。ここは普段からこうなのか?」 頭上の木の枝にダマになっている蟲を見上げながら、ギンコは問う。 「こう、って?」 主語のない言葉に意味を図りかねたしんらが首を傾げた。 「蟲だ。ここは少し多いような気がするんだが――――……いつもこんなモンか?」 問われたしんらは、口に手をあてて考えるような仕草をとった後、ややあって首を横に振った。 「今日は……昨日までより、かなり多いような気がするけど……」 家の中で見かける蟲の数も種類も、昨日までとは違い増えている。屋敷の外に目をはせると、それは更に。 妙な事を言う、とギンコは思った。 突然蟲が増え始めるのに、理由がないはずがない。 昨日までは普通だったと言うのだから、原因は昨日から今日にかけて、何かがあるのに違いない。 「……――――何か、変わった事はなかったか?もしくは、したか」 人にとって些細な事でも、時にはそれが、蟲にとってはとんでもない事を引き起こす原因となる事がある。 何でもいい、とせっつくギンコに、しんらはううん……と唸ったが。 「……かれー?」 「……は?」 突然、一言だけ意味の解らない言葉を発したしんらに、銜えていたタバコを落としそうになった。 「今までになかった変わった事……と言ったら、昨日、女の人が訪ねてきたんだ。 家に帰れないみたいだから泊まってもらったんだけど」 自らの存在を世間から隠さねばならないとは言え、帰れずに困っているという女性を助けずにはいられなかった のだろう、という事はしんらを見ていて良く解る。しかし。 ふむ、と顎に手をあてて考え込むギンコだったが、ある気になる一点に質問を投げかけた。 「帰れない……ってのは、また一体、どういう事なんだ?」 今の所、訪ねてきた女性というのが一番怪しい。しかも此処まで自分で来ておいて、帰ることができないとは。 蟲を寄せる体質の者が、里から追い出されるのは珍しいことではない。この女性も、そういった類の人間ではないのか。 しんらは、訊ねられたその問いに、自分が答えていいものかと思案したあげく、話してしまう事にした。 も困っていたし、必死に故郷のものらしき単語を並べ立てていた彼女の助けに少しでもなれるのなら。 ギンコ、という男は、どこかのらりくらりとしていて掴み所がないと感じたけれど、その穏やかな余裕に 根拠のない信頼感がある。少し中身を残した猪口を下に置いて、息を吸った。 「あのね――――……」 「……はァ」 聞けば、というその女は、昨日気が付いたらこの山の中に倒れていたのだという。 ここが何処だかも解らず、その故郷にしんらの方は心当たりがない上、屋敷を離れるわけにもいかないので 山を降りられるまで此処で過ごしてもらう事にしたのだ、と。 後にも、先にも、突拍子のない話だ、とタバコの煙を吐き出した。 「どう、思う?こんな話に、心当たりとか……ある?」 「さァな……今まで色んな所をまわっては来たが、そんな地名は聞いた事がねェな……」 そう、と肩を落とすしんらを横目に、頭の中で聞いた話を反芻する。 噂にも聞かぬ土地――――そんな土地がまだ何処かにあるなら、人間が移動してこれるのだろうか。 各地を廻る"ワタリ"という職業の連中の口からも、"トウキョウ"なんて響きを聞いた事がなくて眉を寄せる。 「他にも、色々変な名前を挙げていたよ。遠くの人と会話が出来るデンワとか、物が腐るのを遅らせる事が出来る ……えーと……レイ、ゾウコ?……とかいう箱とか」 「あァ?」 気でも、狂っているんじゃないのか、それとも変人じゃないのか、その女は、と、口には出さなかったものの 顔で大いに語ったギンコを見て、しんらはムッとして言い返す。 「さんは凄くいい人だよ。初めて僕の話を理解してくれた人なんだから!」 ああ、やはりな。 呆れ顔を引っ込めて、確信する。察するに、"理解"とは蟲が見える事、強い妖質を持っている、という事だ。 そうなると、という女が、蟲を寄せているのに間違いないだろう。 ここは、その緑の鮮やかさから解るように、光脈筋に違いない。 そんな場所に、と、そして自分という蟲を寄せる者が二人も居ては危険だ。 (こりゃァ、早々に調査を終わらせて立ち退かんとな……そのって女も) 不審なのは、が蟲を寄せるというだけでなく、妙な単語や地名を口にしている事だ。 それも、何かの蟲が原因……なのだろうか。しかし、そのような影響を与える蟲は知らない。 とにもかくにも、会って見なければ解らない。 「な、そのって奴は今は……」 「うぶっ!」 奇怪な悲鳴らしきものと、べション、という音が、西側の裏手の方からした。 「……あ?」 「あっ、またやった!」 思わずぽかんと呆けるギンコを他所に、しんらは物音のした方へとかけていく。 とっさに動けずにいたが、ゆるゆると呪縛をといて、しんらを追いかける事にした。 「大丈夫?またやったの?……本当に、よく転ぶねぇ、さん……」 「め、面目ない……」 滑りこけたと思しき女とそれを助け起こすしんら。そんな光景が、目に飛び込んできた。 しんらの言った言葉から、それが今話に出てきた""だろう、とその人物を見る。 蟲に憑かれているのなら、どんな様子になっているのか、あるいはどんな変人奇人なのかと思っていたが 特に目をひくところのない、普通の女性だった。しんらの家の借り物だろう上品な着物が、いくばくか浮いて見える。 自らの妖質に心を磨耗している様子も見られない。 しかし、そんな事は問題ではない。を見て、ギンコはその違和感に眉を寄せる。 (……人、か?) どうして、そのような事を一瞬思ってしまったのか、解らない。 思い直した次の瞬間には、は人間以外の何者にも見えななかった。 両方見えると言っても、蟲と人間の区別はつく。けれど、どこかしらに、"あちら側"の臭いがする。 知らず、眉間に皺を刻んだまま見ていたが、隠れもせずに目の前に立っているのだからの方も此方に気付いた。 碧色と、茶色の双眸が、ここに来て、再び合わさった。 |
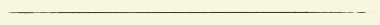
やっと再会させる事ができました。またしてもこのような所で切ってすみません。
←back next→