
おとしもの
目を開ければ、見慣れた天井が広がっていた、なら、よかったのに。 障子を通して漏れてくるのは、昨日と変わらない穏やかな日の光で。 慣れない和室の中、起き上がって仕度をし、蒲団畳んで窓を開ければ。 「うわあっ!」 朝の光を浴びて金色に染まる、何と言うか……形容し難いものが、うようよ。 「……なんか……増えてるような……」 慣れないモノを朝一番で見てしまった所為で、思わず閉めてしまった窓を後ろ手に、呟いた。 今日は、今日こそは………………何をしよう。 先の事を、取り敢えず後回しにした昨日。 回したのはいいが、その“後”になっても状況は変わらず、何をすべきなのかも未だ分からない。 連絡手段も帰る方向も方法も、相変わらず不明のまま。 どうしても家に帰らなければならないという目標はあるが、今のままだと、ずるずると此処でお世話に なり続けてしまう事になる。しかし出す手がないというのが現状で。 「ううぅーん……」 一向に出口の見えない思考の迷路を中断し、味噌汁を煮立たせないうちに釜戸の火から降ろした。 「わ、やっぱりこれも美味しい!凄いなぁ……味噌汁なのに……」 昨日のカレーはやはり一日では処分できなかったため、別の鍋に残してあるが、やはり朝からそんなに重いものを 出すわけにはいかないだろう、と、別のメニューにした。 常温の中、ヤバそうな青葉と豆腐と、限界ギリギリっぽい魚の切り身で、味噌汁と和え物と焼き魚。 しんらはカレーでも全く良いとは言ったが、やはり健康を第一に考えて、ということで献立は決まった。 今回はしんらにとっては馴染みの深いものばかりではないかとは一方的に考えていたのだが、 味噌汁をすすった彼からは感嘆の声が漏れたので吃驚する。 やはり味噌汁の文化が違ったのだろうか。地方には驚くばかりの食文化が存在するとは聞いたことがある。 一応基本は抑えた普通の味噌汁を作ったつもりだ。まるで美食家のように口の中で吟味するしんらを心配気に窺う。 「何かこう……深いっていうか……あー、何て言ったらいいんだろ」 ここまで深く味わって頂けるほど大層なものを作ったつもりがないので、何だか申し訳ないような気恥ずかしいような 気持ちになって、は俯き加減に自分も碗を傾けつつ問い返す。 「……え、えーと……そんなに上手く出来てたかな」 そりゃまあ、味噌の他に何かと言われれば、出汁が入っているが。それもスーパーで買った粉末出汁が。 本来なら昆布や煮干などで出汁はとりたい所だが、この状況でそうも言ってられない。 してその出汁にしたって特別な事などない。 味噌汁を作る上で出汁をとる事などは当たり前だし、粉末出汁にしたって普通のカツオ出汁で… カツオ→海。 此処→いっそ誇れるくらい山。 川魚の淡い上品な味わいでは、この出汁は出るまい。 「…………あー」 そうか、と遠い目をしながら一人で納得しているを他所に、海の幸など引篭もり生活の中では そうそう口にする事のないしんらは、焼き魚をつまんで頬を綻ばせ、嬉々としておかわりを要求している。 料理は、どちらかと言われればまあまあ得意な方に入るが、過剰評価が後で怖い。 「―――――これ位で、足りる?」 「ああ、ありがとう。もう充分だよ」 使わない布はないかと問われて、しんらが古くなった着物などを持っての部屋を訪れた。 昨日転んだ拍子にビニール袋を破いてしまったので、残っている荷を持って帰るために使う鞄を作ろうというのだ。 その旨を伝えた時にしんらが少しだけ見せた寂しそうな表情を、古着を手渡してくれる際にも ちらりと見てしまったので胸が痛んだ。 こんな自分を慕ってくれるのは本当に嬉しいのだが、実家へ連絡も入れずに他の家に居座るわけにはいかない。 「家に帰れたら、また……ここに来させて貰っていいかな。絶対に誰にも言わないから」 その言葉に、満面の、とはいかないが、しんらは嬉しそうに笑って「もちろん」と頷いてくれた。 「……でも、今のところ、帰る手立てが無いから…お世話になっちゃう事になるんだけどね……」 ごめんなさい、と が頭を下げると、お互い気の早い話をしていたのだという事に気付いて、苦笑いをし合う。 「さてと、それじゃあ僕、部屋の方で書き物をしてくるから」 そう言って立ち上がったしんらは、小脇に筆入れや紙を抱えている。しかし右手の包帯は巻かれたままだ。 まさか。 「……左手で、書くの?大丈夫?」 「うーん。字なら……大丈夫かな、と思うんだけど……多分」 どうやらその根拠の無さそうな態度は、初めての試みだからということらしい。 (……ま、まぁ……誰も来ないだろうし……変なのが一つ二つ増えたって大丈夫、かなぁ) いったい、描いたものが生命になると、どんな生き物が生まれるのかは知れないが。 「……えーと……健闘を祈ってるよ」 心配そうに見送るを背に、楽天的に笑いながら、しんらは部屋を出て行った。 そうして、しんらの足音が遠ざかってから。 「あれ、廉子さん、出かけるの?」 実はやや二人斜め後ろに居て動向を眺めていた廉子なのだが、ふと気が付いたように窓に手をかけたので声を掛けた。 「ん……ああ。何か、気配がする。散歩がてら見てくるよ」 意識はその“気配”に向いているのか、やや気の無い答えが返ってきたが、 の方も針に糸を通す作業に没頭しかけていたので「そう」というだけの返事をした。 ふわりと飛び上がった少女の背に、いってらっしゃいと投げかけたが、針に糸を通した後で、己が異常に対して 大分順応が進んだ事に気付いて嘆くのだった。 「……ん」 こつ、と足先に石ではないものが当たるのを感じて、その正体を確かめるべく身を屈める。 だが、それはかなわなかった。“それ”を見ても正体が分からなかったからである。 「何だこりゃ……」 草の陰に転がる異質で人工的な光沢を持った「それ」は見たことがないものだった。 何に使うのか、それ以上に何なのか皆目見当もつかない。 手の平にのる大きさの硬質なもの。鉄、というわけではなさそうで、けれど他のどんな鉱物とも違うもので出来た塊。 しばし考え込んだが、「珍しいもの」に相違ないし、そういった物は採取したがる癖も黙っていなかったので拾う事にした。 役に立たないものでも、どこかで、それこそあの偏屈物の蟲収集家に売れるかもしれない、と荷の中に放り込む。 するとその時、視界の端に、木々の合間を移動する何かが映った。 けれどもそれは一瞬で、こちらが辺りを警戒して見回しても、再びその姿を捉えることはできない。 「何か今、いたな」 あちらも気配を消しているのか、かさりというも音もしない。 「……猿かね」 言われた本人が聞いたら激怒しそうな言葉を吐いておいて、男は気に留める事無く先へ進む事にした。 こんな場所だ。何がいてもおかしくない。それこそ鳥だって、獣だって、あるいは…それ以外の何かだって。 「……しかし」 歩きながら、頭上を覆い尽くさんばかりの緑の天井を仰ぎ見て感嘆に息をつく。 「緑が異常なくらい鮮やかな所だなここは……」 そうして、視線を下ろして辺りに漂う常人には見えない“ソレら”にも目を向ける。 「……―――少し、多い気がするが……」 自分が蟲を寄せ付ける性質を持っていると言っても、その全てを理由には出来ない程の数である。 踏み込む先には既に蟲が集まっていて、目的地に近付く程に僅かずつであるが増えていっている気がする。 (……蟲を寄せる人間だとは聞いてないがな……第一、それならこんな場所に定住できない筈だ) そういった体質を持っているのなら、ここまで生命が栄える土地に長く居れば何かしらの異変を起こしてしまいかねない。 (まァ……会ってみりゃ解る事か……) 思考を中断し、吸っていた煙草の煙を吐き出すと、荷を背負いなおして足を速める事にした。 「いづッ……」 プツッ、と指先に鋭い痛みが走り、思わず左手の人差し指を口の中に入れた。 家事は普通に出来ると自負はしていても、手縫いはその範疇外である。 遊び感覚で作れるようなマスコットや小物以外、実用的な鞄などの道具を作るのには大体ミシンを使って いたので、自分みたいな素人が完成までに一回も失敗しないというのは、まずない話だ。 極力、無駄を省いて、荷物が入ればいいだけの最低限な鞄作成は、思ったよりも先に進まない。 山深いここから麓までは、きっと徒歩になるだろう。適当に作れば、その途中壊れてしまいかねないので なるべく頑丈に作ろうとしているのが、作業の遅延の原因か。 今のところ、早急に完成させなければならない理由は無いからいいが。 (ああ、もう……しんら君には悪いけど、本当に不便だなあ、ここって……電化製品一切その他何も無いし。 ……時計もないから、今何時なのかも解らないよ……) ぱっと見上げた先に、大抵はあるはずの時計も此処には見当たらない。 そもそも時を知る目安が、日の傾き具合と腹の調子しかないなんて。慣れない感覚にそわそわする。 「……ん?」 その時、いつの間にか銜えた指から舌に広がる味の違和感に気付いた。 針で刺した部分から滲み出た血だというのなら、独特の鉄くささが口内に広がっているはずなのに。 (……何か……甘い) 先程料理を作っていた時、どこか、何かがこぼれていた所にに手が触れていたのだろうか。 指に、甘い味がこびり付いている。 不思議な事に、痛みが無くなっていたので口から離すと傷はおろか、痛みの名残さえない。 もう一度舐めてみた指は、何の味もしない普段通りの自分の指だった。 「……気のせいかな。ちょっと深く刺しちゃったと思ったけど……」 それにしても、一度気になりだすと、そちらに気を取られて作業が散漫になってくる。 いったい、今何時なんだ。 前回は傷は浅かったが、気が散ると二度目の失敗では本当に血を見るかもしれない。 (お昼ごはんも、いつごろ用意すればいいのか解らないし……) 息をついて進まない手を止めると、部屋の隅に置いてある大学の通学に使っている鞄を手繰り寄せた。 「あっ、アンタ達はまた!もう……ここに住まないでって言ってるでしょ……」 ちょこん、とごく小さな蓮の蕾に小さな足が付いたような蟲が、鞄の上に数匹乗っかっている。 初めて見つけた時は慄いていたが、何度掃ってもいつの間にか居座っている。 980円ワゴンセールで叩き売られていた地味な鞄は、その蟲達にいたく気に入られたらしい。 もうなかば諦めて、邪魔しないでやらない事にした。まだまだ不気味な所はある彼らだが、 何だか愛嬌もあるような気がして、苦笑が漏れる。 取り敢えずそいつらに影響がないように気を遣いながら鞄を開け、中身を漁る。 折畳み傘、ペンケース、ルーズリーフ……目的のものはなかなか見つからない。 (あれー?どこにいっちゃったのかな……携帯……) それがあれば、今日の日付も、時間も、バッチリ分かるのに。奥のほうに潜り込んでいるのか。 「うーん……どこに――――……ん?」 自分が捜している物について、もう一度よく考えてみた。 「……ぁ」 携帯―――――電話。 「あぁあっ!」 がさぁ、と、叫ぶと同時に鞄を逆さにし、中身をぶちまけた。当然乗っかっていた蟲も一緒に落とされ、 何だ何だ何が起きた、とでもいうように引っくり返って足をわたわたさせている。 ゴメン、と呟きつつ、もう鞄に何も入っていない事を確認してから散らばった物を掻き分けた。 どうして気付かなかったのだろう、自分は家に繋がる手段を、たった一つだけ持っていたという事に。 恐らく、こんな所で電波が拾える事はないかもしれないが、万が一、臆が一、という事もある。 「な、ない……ない……どこにいったんだろう……!?」 もう一度、鞄の中、ポケットを捜し、買った荷物の置き場所も、着ていた衣服のポケットも、思い当たる場所 全てをくまなく捜したが、見当たらない。あの日は、家に携帯電話を忘れて来ていた…? いいや、帰り道で電話したのを覚えている。 「今から帰るから」と言って、電話を切ったのだから、更に余計な心配をかけていることだろう。 ここでは繋がらないにしても、麓へ降りる事が出来て、そこから連絡出来れば万事解決なのに。 「……やっぱり、ない!」 見つからない。かけた時の記憶以降、どこへやってしまったのか。 ここにないとすると、可能性は一つだけ。 昨日、気が付いた場所―――――そこに落としている可能性が、かなり高い。 は急いで作りかけのものと、裁縫道具をしまい、外へ出ようと戸に手をかけた。 「そんなに慌てて、どうしたんだ。出かけるのか?」 声のかかった方を振り返ると、散歩が終わったのか、不思議そうな顔をした廉子が窓から入ってくる所だった。 「ああ、お帰りなさい、廉子さん。あの、昨日いた場所に落し物をしてきたかもしれないの。だからちょっと捜しに」 もしかしたら、獣に持って行かれてしまうかもしれないし、夜露か何かにやられてしまうかもしれない。 いずれにせよ、土の上に長く放っておいていい事はないだろう。急がねば。 「そうか。それなら、屋敷の西側から行った方がいい。足場は無いに等しいが、真っ直ぐ行けば早く着く」 どうして歩くのに慣れない自分に廉子は道なき道の方を示したのだろう。森なんて同じ景色にばかり見えるし、 昨日倒れていた場所の特定は難しい。困った顔のを見て、廉子は苦笑いをした。 「東側の道から、妙なヤツがここへ向ってるみたいでね。ついていてやりたいが……なに、転ばないよう 気をつければ、そう険しくも無い。場所は、二股に分かれた木と、その横に腰掛くらいの岩がある所だ」 ……妙な奴? 案内は有り難いし、こちらは多分大丈夫だろうとは思ったが、捨て置けない言葉が廉子の話の中に混ざっていた。 警戒を強めて眉を寄せたを諭すように、心配ない、と廉子は首を横にふる。 「この間、ギンコとかいう蟲師から調査依頼の書簡がきていた。多分そいつだろう。 そういうのは追っ払うよう、あの子には言いつけてある。私が見ているから、お前は行って来るといいよ」 何かあっても、ここに大人は他にいないのに。なおも心配そうな顔をしてみせたが、廉子は肩を竦めてみせるだけだった。 「妙なヤツといっても、危険そうではないから」とそう言って、送り出して、もらったのが。 一日ぶりに土の上に足をのせる。相変わらず、仄かな緑色の優しい木漏れ日、木々の擦れ合う音、穏やかな空気。 急いでいるのにも関わらず、思わずうぅん、と伸びをしてしまった。もやもやした思考をそれで吹き飛ばす。 マイナスイオンが充満していそうな辺り一帯に目を馳せると。 (うわ……いっぱいいる……) さくさくと草を踏みしめながら、辺りを淡く発光する蟲達が漂っているのを横目に流していく。 (でも、慣れると……綺麗かも) 正体が分からないと不気味だが、しんらいわく、光るものはそんなに悪いやつではない、という事らしいので 見ようによっては幻想的で美しい。の知る「虫」よりは、「蟲」の方が見ていて苦手ではないかもしれない。 けれど、"悪いやつじゃない"というのなら、悪いやつもいる、という事だろう。 そのために、蟲師という存在があるのではないだろうか。 廉子の言った蟲師の言った事を思い出しながら目的地へと向う。 (ギンコさん……響き的には銀子さん、かな?……じゃあ、女の人なのかな) ドテッ!と、廉子の忠告も空しく、悪い足場に何度か転びながら歩を進める(何だか慣れてきた)。 そして、また突然、はたとある事に気付く。 (この山を降りるなら、その銀子さんに着いて行けばいいんじゃ……?) 最初はぼんやりと思い描いていた事が、あまりにも的を得ている事に気付いて、はっとした。 どうしてこうも、うっかりしているのだ自分は要領の悪い遠回りばかりをしているんだろう。こうしてはいられない。 一刻も早く携帯電話を見つけて戻らねば、銀子さんが追い返されてしまう! 慌てて駆け足に切り替える。 色んな所にぶつかりつつ、引っ掛かりつつ、目的地へは廉子の言った通り、すぐ着いた。 二股の木と、腰掛くらいの岩がある、比較的ひらけた場所。 変な感じがした。 拉致されて、ここに放り出されたという割には、人に侵された事のない美しさを保っている。 車で来れるような場所でもなく、その痕跡もない。犯人がいるのだとしたら、どうしてここまで、どうやって? 「……って、捜さないと」 とにかく今は、それよりも、だ。 ざっと辺りを見渡し、次に草の陰、木の裏側、しらみつぶしに探し回ったが、見つからない。 まさか、もう獣が銜えていってしまったのだろうか。 (……やっぱりないな……もしかしたらあの帰り道で、落としてるのかもしれない……) 気絶させられたとき、その場に落としてきてしまった。 あるいは犯人に取り上げられてしまった、というのは、充分ありえる。 見つからないものは仕方ない。いい加減に諦めをつけて戻る事にしよう。 下界へ繋がる銀子さんの方を優先しなければ、元も子もないのだ。人がいる場所に出てから、あとの事は考えよう。 踵を返すと、もと来た道を急いで戻る。 こんなにも早く、「これからどうするのか」が解決してしまうとは思っていなかった。 呑気な事に、暫く先、しんら達と過ごしている自分を想像してしまっていたのだから。 ―――――ここに、留まってはくれないか ―――――僕はとても、嬉しかったんだ 廉子の言葉と、しんらの顔が、脳裏に浮かぶが、苦しくもそれを振り払った。 胸が少し痛むが、けれど。自分には放っておけない現実や家族がある。 一度帰って、それからまたお礼に来させて貰えばいい。そう思う事にした。 そうなれば、しんらも廉子も、一人ではない。きっと。 |
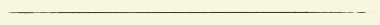
七話目にしてやっとギンコさん再登場
←back next→