
居るべき場所は
「……えーと、たしかばぁちゃんの荷物は此処に全部………あ、あった!」 使われなくなって久しい部屋で、しんらがタンスを開けたり閉めたり。 取りあえず灯りを持って、は彼のやや後方に、申し訳なさそうに待機していた。 「よっこいせっと……着物はこの三段にしまってあるみたいだけど………ああ、こっちは子供の頃のヤツだな」 持ち主が亡くなってからも、捨てられずに丁寧に仕舞われたままになっていた小物や着物。 少しだけ埃っぽいにおいを醸し出しながらも、綺麗なままで残っている。 どうしてそれらが再び日の目(今は夜だが)を見る事になったかというと。 「あの……本当に、いいよ?このままで寝られるから……」 「いいからいいから。どうせこれから先使われる事なんてなかったろうしさ。そのままだと寝苦しいでしょ?」 コートは脱いでいるとしても、冬用のアンダーにボトムを身に付けている。 ここの気候に対してその格好を寝間着にするには、いささか分厚い。 着替えなんて持っているはずも無くて。 そこに気遣いの達人であるしんらが、お祖母さんが使っていた着物はどうか、と提案してきたのである。 大事に仕舞われてあるものをひっくり返すことはない、と遠慮はしてみたものの、結局引きずられるような形で今に至る。 客人もただでさえ珍しく、こと親しくやりとりが出来る相手に、しんらははしゃいでいるように見える。 「うーんと……こっちはちょっと寝るにしては派手だなあ…… さん何色が好み?あ、こっちの段のヤツの方がいいかな?」 がさごそと引き出しの中を漁っては、あーでもないこーでもないと品定めをしているしんら。 別に寝るだけなのだから、本当に最低限のものでいいのだが。 は苦笑しながら、こだわり続けるしんらを横目に乱れた着物を直しにかかる。 やはり屋敷も立派なだけあって、品の良い物が仕舞われている。しんらのお祖母さんが子供の頃に着ていたという着物は 残っている数は少ないものの、捨てられるには惜しい程のものが残されていた。 防虫・防カビ剤などが使われていないし、紙に包まれただけという状態なので少し色褪せていたりするが、 一着一着を紙で丁寧に包んである。確認のために、無情にもそれはしんらに剥がされてしまっているけれども。 それを包み直そうと手を伸ばした。 「―――――……」 触れようとした指先が、止まる。 妙な違和を感じた。 これは、しんらのお祖母さんの着物。それ以外ではありえない筈。 なのに。 ふわりと、その着物の袖が翻っているのを見た記憶があった。 頭はその解りきった事実を、答えを導き出そうとしている途中なのに、勝手に口はその解答をしんらに求めていた。 「ねぇ、しんら君………お祖母さんの……名前、は……?」 候補を何着か腕に抱きながら、引き出しの中を物色する手を止めてしんらは顔を上げた。 急に脈絡のない事を聞いてきたを不思議そうに見ながらも、何でもない事のように、答える。 「廉子……五百蔵廉子、だよ」 暗い天井を照らすのは、枕元に置かれた薄暗い灯だけだった。 ぼんやりと浮かび上がる木目を見ながら、今日一日の事を考える。 痛いほどに目や頭を中心に疲れた日だったと、思う。 環境の激変は勿論、体験した事もないような出来事、見たこともないモノ達、自覚する事のなかった感情。 考えても考えても、整理が追いつかない。 理屈で片付けようとするから、こんなに苦悩しなければならないのだ。 ありのままに受け入れられたなら、非科学的、非現実的という言葉は、不思議や奇跡という言葉で片付けられる。 けれど、そうなってしまったなら、帰路は遠く霞む。もしかしたら存在しないかもしれない。 恐ろしくなって首を振り、まだ諦めるもんじゃないと強がってみる。 そう、もしかしたらコレが全部、夢だっていう可能性もあるのだから。 蒲団に横になって寝る体勢にいるわけだから、本当に夢だったら馬鹿みたいだけれど。 「どうだ、。しんらと随分仲良くやっているようだね」 声が聞こえた方向に顔を向けると、やや右手の天井に廉子がいつの間にかいるのが見えた。 「廉子……お祖母さん」 のその言葉を聞いて、浮かべていた笑みを一瞬引っ込めた廉子だったが、溜息をついた後苦笑を浮かべる。 そうしてふわりとの傍に降りてきたが、足を床に付けずにそのまま浮遊している。 「しんらから聞いたんだね。……その様子だと、左手の事も、蟲の事も話したんだろう。まったく、あの子は口が軽い」 咎めるように言う口調も、どこか優しく、保護者の色を滲ませている。 軽く笑ったを見て、廉子も目を細めて笑んだ。 「昔、色々あってね。私はしんらが生まれてからずっと見ていたけれど、あの子があんなに楽しそうなのは初めてだよ」 色々、と廉子は遠い目をして簡潔に済ませたけれど、たった二文字では説明がつかないのは様子からして明らかだった。 しんらの話では、彼女は4年前に亡くなっている。 なのに、幼女の姿でしんらの傍に留まり、けれど霊とかそういう類のものではない。 かといって蟲だというわけではないから、それらを見ることのできるしんらであっても、廉子がここにいる事を知らない。 「お前みたいに妖質を持った人間と接するのが初めて、という事もあるんだろう。ただでさえこんな所に人は来ないしね」 孫の事を話す廉子の目には愛しさが称えられていたけれど、同時にそれと同等の悲しみも含まれている。 「見守っていた」という表現を使わなかったのは、本当に見ている事しか出来なかった故だろう。 彼女が今の現状を良しとしていないとも捉えられないだろうか。 「……しんら君は、とても大事そうに、廉子さんの事を話してた。誰とも接する事の無い生活の中で…… 廉子さんの存在は、本当に助けになってたんだろうと思う」 たかが今日転がり込んできたばかりの、しかも自分を肯定できない臆病者には過ぎたる言葉だった。 謙遜からではなく、本当に自分にそんな感情を持ってもらう資格なんてないと思った。 ともすれば、後ろ向きな事ばかり考えていて、崩れそうになる所を助けてもらってばかり。 そんなの心情には気付かずに、廉子は穏やかに続ける。 「……しんらのためになると思ってたにしろ、私はあの子の見えるものを否定してきたからね。 あの子が、本当の意味で笑ったのを見たのは、初めてだ。同じ感覚を分かち合える人間と出逢えたんだ。嬉しいんだろう」 「…………」 言葉に、詰まった。 同じ感覚だ、などとは、到底胸を張って言えるもんじゃない。 心の中では、きっと廉子がしんらに浴びせていたであろう否定の言葉を叫んでいる。 ただ、しんらの笑顔を曇らせるのが恐くて、言えないだけ。 まだ、彼らの存在に戸惑ってばかりいる。 「……ありがとうな、」 言ってもらえるはずのない言葉に驚いて、顔を上げる。 もうこれ以上は、良心が痛む。 そうしていっそのこと、そんな無価値である自分を打ち明けてしまおうかとするを、廉子は笑みで制した。 解っている、というかのように。 「それでも、お前はしんらを否定しなかったろう? 私は、少なからずよかったと思ったよ。この家に連れて来たこと」 結局は困っている人間を方っておけなくて、家に連れてきてしまったのだが、正直不安はあった。 人と蟲の中間である自らの事も、常人には見えないモノを見る特殊能力持ちの孫の事も、 普通だったら受け入れられないだろうから。 それを目の当たりにして恐れをなして逃げるのならば、そうすればいい。 ここは旅慣れていない者が案内無しにはうろつく事が出来ないくらい深い山だ。 そう構えていたが、浮遊する自分を見て、多少脅えながらも結局ついてきて、 繕ったものとしても、何も否定しないの様子に、それが杞憂であると判った。 例え表面だけだったとしても、はなから化け物だとして全面否定してくるような人間でない事 だけでも、充分だった。が蟲に対して抵抗を持っているのは解る。けれどそれを、しんらの前では否定しない。 普通の人間に変わりは無いけれど、どこかで感じるという人間に対する違和。 どこか、この雰囲気は異端に感じるのだ。自分達と、蟲と、似ている気がする。 「あの子は、上っ面だけの人間には、あんな風に嬉しそうに笑わないよ」 それを言われて、今度こそは心の中がこそばゆくなるのを感じた。 そんな風に言われたのは生まれて初めてなのだから。 どこが、よかったのだろう。思い返してみても、与えられるばかりで自分は何にも出来ていない。 そうだ。自分は、自分を誰かに知ってもらう事が、下手糞だった筈ではないか。 なのにどうして、ここに来てからこんなにも素直に他人と接する事ができているのだろう。 やはり、しんらの、廉子の人柄のお蔭に違いないのだ。 「……ううん。多分、お礼を言うべきなのはこっちだから。本当に……嬉しいです。ありがとう」 心の芯が、じん、と温かくなるような感覚だった。 行灯の火が揺れる。 暖かい感覚を覚える沈黙が、次第に温度を失ってきた頃、一瞬の戸惑いの色を滲ませた後 廉子はこちらに顔を向けて、真っ直ぐとの瞳を見据える。 「……なぁ、。お前、ここに留まってくれる気は無いか?」 ぽつり、と、呟くように言われた割には妙に存在感のあるそれを、は一瞬飲み込めなかった。 「……え?」 問い返したに、今度は形を変えて、より伝わりやすいようにと廉子は訴える。 「もしも帰る家が遠いのなら……或いはもしも、ここから遠くないのなら……しんらの傍に、いてやってほしい」 「………」 ただ目を見開いて。それは、時間をかけてじわじわとの中に染み渡っていく。 一人の人間として受け取るには、とても光栄な言葉なのかもしれない。 けれど、それを上回る重さを持っていて、そして、決して首を縦に振る事は出来ない言葉でもある。 「いや……それは、しんら君がどう思うか、だし……私なんか」 「あの子はきっと、お前にここにいて欲しいと思ってる」 「で、でも、私は……今日ここに来たばかりだし。だから……そんな」 視線を逸らし、翳らせた顔でが「できない」と言葉を発する前に、廉子は尚も食い下がった。 「けれど、お前がここを去った後、しんらはまた、一人になる」 なんのことはない。少年はまた、以前の生活に戻るだけ。 けれど、一時だけでも触れた温かみの記憶を、一人きりの一生の中で留めておくのは少なからず、辛いこと。 そうして、時折寂しそうにするしんらを、傍にいながら眺め続ける事しかできないのも、廉子には辛いことだった。 これから先、しんらが廉子の言いつけを守る限り、死ぬまでずっと。 生物世界の均衡を崩しかねない力が、ひっそりと、この世から無くなるその時まで。 それを全て、見続けなくてはならないのだ。 どんなに手を伸ばしても決して届くことのない、ごく近い場所から。 悲痛に顔を歪ませる廉子を見て、その言葉から、廉子の辛さが伝わってきて。 はとても苦しくなった。助けてあげたい、とも心から思った。 助けてくれた廉子やしんらに、できる事ならなんでもしてあげたい。 けれど、彼女の一番の望みを叶えてあげる事はできないのだ。 ここではない故郷に、大切な、自分を育ててくれた家族がいる。そこへ帰らなければならないのだ。 他に何か、できる事はないのだろうか。何でもいい。小さな事でも、彼女達の辛さが和らぐ事なら。 「私が……私が、伝えましょうか。ずっと、傍に、廉子さんがいるんだって事を……」 自分の傍にある存在を、知っているのと、知らないのとでは歴然とした差が有るはず。 姿は見えなくても、お互いを大切に思う存在が近くにいてくれているのだと分かっているなら。 必死のの言葉に、廉子は悲しそうに、ふるふると首を横に振った。 「見えないものを否定してきたのは他でもない、この“私”だったんだよ」 |
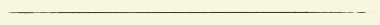
家や家族のこと、簡単に忘れられないと思います。
←back next→