
孤独の秘密
「お……おいしい!おいしいよコレ!僕こんなの食べた事ない…!」 匙を運ぶ手が止まらない、という勢いで、碗の中を夢中で掻き込むしんらを見て笑みがこぼれる。 やはり無条件で泊めてもらうのには気が引ける、という事で、家事をやらせてもらう事にした。 あくまでも遠慮するしんらだったが、どちらにしろ右手を怪我しているのでは不便だろう、という事で説き伏せた。 手始めにが任せてもらう事になったのが、夕食作りである。 家事は得意な方だが、実質ここまで褒めてもらえるような、人を感動させるまでの腕前を持っているという事はない。 実をいうと、この鍋の中身、カレーである。 案の定、「東京」という言葉が通じない彼には「カレー」も通じなかった。 買い物係の特権というやつで、ルーは自分好みの甘口よりのもの。 スーパーの特売で大箱80円大特価。5箱セットで325円の超お得目玉商品だった。 この様子だと食べ物の文化も違うかもしれなかったが、 老若男女問わず人気メニューのカレーなのだし口に合わない事はないだろう。 そう思って作ってみたのが、思いの他予想を大きく上回る高評価だった。 察するに、普段の食事は台所の様子からしてもっと薄味だろう。 正に時代劇に出てくるような、それはもう原始的な厨という場所に、 は苦戦を強いられた。 調味料が云々というレベルではない。釜戸で飯を炊くなんて、初めての経験だった。 栄養が一番で、味なんて後回しだろう食文化とは逆の趣旨で作られた固形調味料は、彼の舌を大いに驚かせた事だろう。 こんなに喜んで貰えるなんて、作った甲斐があるというものだが、実際の手柄は某食品メーカーなので複雑である。 炊飯ジャーも、ガスコンロも、電子レンジも無いとくれば、冷蔵庫などあるはずも無い。 が、そんな事態を考慮されていない鮮生食品が危ない。 その事も含め、ある程度色んな物をつぎ込んでも問題なく、且つ量産できるものというわけでメニューは決定した。 今現在の、この夏と思しき気候では、一日放置するのも危険かと思われる材料を注ぎ足したため、かなりの量になる。 それでも嬉々としてお代わりを要求してくる食べ盛りの少年の様子なら、腐らせてしまう前に処分は出来そうである。 茶色の液体の中に沈むキャベツの破片をつつきながら苦笑した。 木で出来た匙で、一口ずつすくって食べていると、思い出すのはやはり家の事で。 が買って帰る予定だったので、当然冷蔵庫や棚の食材などは少ないままだろう。 財布の中身は少ないものの、キャッシュカードが入ったままだ。 しかしそんな事を気にかけている余裕などないくらい、家族は心配をしてるかもしれない。 いいや、きっと、している。 とても、とても迷惑をかけている。 これ以上、苦労をかけたくないのに。 私のせいで、家に負担をかけたくないのに。 「……さん?」 ふいに呼ばれてはっとすると、しんらが手に匙と碗を持ったまま不思議そうな視線を向けている。 こちらの手元と顔を交互に見るその様子に、はやっと食べる手が止まっていた事に気付いたのである。 どんどんと沈んでいく思考の中、最悪に陥る一歩手前で引き戻してくれたしんらには、そんな気はなかったろうが 結果として随分と助けてもらっていて感謝の念を抱かずにいられない。 「あ、ええと、ごめんなさい……何でもないんです」 慌てて苦笑すると、取り繕うように止めていた食べる手を再開させた。 随分とお世話になっているのだし、これ以上こっちにも気をつかって貰うわけにはいかない。 そう思って選んだ言葉も、この少年には通じなかったようで。 「……家のこと?」 窺うように見ていた少年が、食事の手を下ろしたまま、ぽつりと問いかけてくる。 「やっぱり、家族が心配だよね……突然のことだし。ごめんなさい……何もしてあげられなくて……」 見事にこちらの心境や、考えていたことを言い当て、今度はの代わりにしんらが沈んでしまった。 「そんな、とんでもない!五百蔵さんにはこんなにお世話になってしまって、感謝してもし足りないくらいなんですから!」 今こうして暖かい食事を、和やかな会話と一緒にとる事が出来るのに、それを幸運だと思わずして何とする。 それもこれも、しんらのお蔭に他ならないのだから。 心から訴えると、今度は逆に慰められてしまうような形になったしんらは、決まり悪そうに苦笑した。 その笑みに、も出来る限りの笑顔を返す。自分は大丈夫だ、と言うように。 がこうして気を落とせば、それを見てしんらが何も出来ないのだと、自分を責めてしまう。 そういう、子なのだ。この子は。 こんな、右も左も解らないような場所で、こんなにいい人と出会えた事は本当に奇跡という他ない。 自分は、大丈夫。何の心配もいらない、最良の環境にいる。 それを家族に伝える事ができたらよかったのだけれど。 「ねえ、さん」 「何ですか?五百蔵さん」 食後、片付けを済ませてお茶を煎れているに、ぽつりとしんらが声をかけた。 それにが返事をすると、しんらは少し眉を曲げて妙な顔をした。 「その、敬語と“五百蔵さん”ていうの、やめてほしいな……僕の方が年下なんだし」 昼の、あの出来事を切欠として、しんらはに丁寧語を使うのをやめている。 そうなっても聡明そうな雰囲気は変わらないが、時々口を尖らせたりして年相応の表情をするのを見ると、微笑ましい。 「そっか……じゃあ、しんら君って呼ばせてもらうね」 お世話になっている身としては、家主というわけだし一応態度を変えないでいたが、当人からの申し渡しとあれば断れない。 正直タイミングを掴み損ねて困っていたし、ありがたい話だ。 しんらはの返答に満足して頷くと、お茶を受け取って一口飲み込む。 そうして一拍の間を置くと、自身の言葉を、一字一句確かめるように話し始めた。 「さんは見えてるって、言ったよね。あのふわふわしたのや、ぼんやり光っているモノが」 「……うん」 夢に見たものを語るように、湯飲みの水面を見つめながら紡がれる言葉。 此方が頷いたのを確認すると、自らも頷いて、そうして一度目を伏せる。 次に彼がゆっくりと瞼を開いた時には、何らかに対して意を決したような雰囲気があった。 「……僕がここを離れられないのは、ばぁちゃんの言い付けだからなんだけど、それには理由があるんだ」 茶の水面を通して、どこか遠くを見ているような解らない目だったが、しんらのそれには 覚悟を決めたような光があって、は傾けていた湯飲みを離し、姿勢を正して聞きに入る。 しんらはまた間を置くと、視線を下げて自分の左手を見た。 「僕には、人と違った性質があって、それを決して広める事のないように、眠らせておくようにするためなんだって……。 ……だから僕はここを離れられないし、人と接するわけにもいかない……」 左の掌をずっと見ながら話す彼を見て、もその“理由”がそこにあるのだという事を、何となく察した。 の視線が己の左手に移ったのを見て、しんらは続ける。 それは、ずっと秘めてきた事。最大の、知られてはいけない秘めなければならない事。 「僕がものを描くと、それがどんな形をしていても生命を持ってしまうんだ」 は思わず、息を呑んだ。 そんなの反応を見るのが恐いのか、そこで口を止めてしんらは俯いている。 静かだけれども熱のこもった言葉には、嘘も冗談も、どこにも交じりこんでいない事が窺える。 信じられないけれど、事実でしかない。 本当、なのだろう。 我ながら、あまり抵抗無くはその事を受け入れられたように思う。 非現実の連続で、もう何が起ころうが不思議じゃないくらい感覚が麻痺しているんだろう。 でなければ、彼の言った事に対して「凄いな」なんて感想は持たなかったろうから。 「……凄い、ね」 思ったとおりの感想が口をついてでると、それにしんらは反応して、恐々と顔を上げた。 「信じて、くれるの……?」 「しんら君も、こんな素性の知れない私の事を信じてくれたんだもの。だから私も、君の事を信じられるよ」 誰かを、家族以外の他人を、「信じる」なんて。ふざけて言ったり、上辺だけの言葉の遣り取りはあったかもしれない。 けれど、こんなにも心底素直に腹から他人を信じている事を伝えるのは、今が始めてだ。 今までの冷たさを感じる社会では、その言葉とは無縁すぎた。 彼は、受け入れてはならないと言いつけられていたのにも関わらず、突拍子のない状況の自分を招き入れてくれた。 だから、素直に受け入れる事ができた。 或いは、彼の方もその逆だったのだろう。信じ難い力を持っていたからこそ、の話にも抵抗がなかった。 そういう風に、お互いの間に信頼を感じられるというのは、何て暖かい気持ちになるのだろう。 しんらが安心したように、嬉しそうな顔になったのを見て、またさらに暖かくなる。 今日会ったばかりの相手なのに。 「でも……どうして、私に?広めちゃ駄目な事なんじゃなかったの?」 問うにしんらはにっこりと笑顔を向けた。 「あなたには、アレらが見えるんでしょ?」 さっきと同じ問い掛け。 指を指された方向を見ると、先程部屋で見かけたものと同じ花のような生物が、床にへばり付いている。 だがそれが何の理由になるのだろうと、納得のいかない気持ちを含めた視線をしんらに戻す。 「僕にも見えてる。けれど……普通の人にはそれが見えないんだって。……ばぁちゃんもそうだった」 やはり、常人には見えないものなのだ。 自分はしんらの言う、「普通の人」のど真ん中に位置する場所にいるような人間だと思っていたのに。 「僕は“アレら”が存在する事が、とても嬉しかった。けど……ばぁちゃんは違った。ばぁちゃんだけじゃなく、人にとって それは見えない分、曖昧で存在すらしない幻なんだ」 見えないものがその辺に沢山いる。 見えていない者にとって、それはおぞましいモノだという以外に何ものでもないだろう。 けれど、にはそれが見えた。 原因は解らなくとも、それらは見えてしまったのだ。 彼らは直接介入してこようとはしない。 ただ其処にいて、ひっそりと確かに息づいている。 愛しいとは思えないが、それらが否定されるのはどうしてか、とても悲しい事だと思った。 どんな形をしていても、それが命の形だというのなら、誰にも否定されてはならないのだから。 「見えるか、見えないか。違いはたったそれだけなのに、溝はあんまりにも深かった。どうしても分かり合えないのが寂しかった。 こんなものを見ている自分の頭がおかしいのかもしれないと思っていたけれど……違ったんだ」 彼らは、ちゃんといる。感覚を分かち合える者に出会えて、確信することができたのだ。 人と関わりあってはならぬという業の中で、確かめたかった生命のかたち。 わかちあえぬ寂しさを拭ってくれるものを、ずっと、諦めながら待っていた。 「さんも同じものを見ていると解った時、僕は、とても……とても嬉しかったんだ」 だから話せると思ったと、しんらは照れくさそうに笑った。 はそう言われて、気恥ずかしいような、申し訳ないような気持ちになる。 自分はついさっきから見えるようになったのだし、どちらかと言うと、彼らを見ていて嬉しいなどとは思えない。 感覚は同じでも、その受け取り方は見えていない人のそれと変わりはなかったから。 そんな風に思ってもらえる資格など、秘密を明かしてもらえるような立場などでは、きっとない。 でも、それを言うのが恐くて。 歩み寄っていけたら、と思う。不思議な彼らの存在に。 しんらが愛しいと思うのだから、彼らはきっとそれだけの魅力を秘めている。 もっとも、家に帰るまでの時間に、そうなるまでの余裕があればの話だが。 どうして、自分は突然に見る事のできる権利を得ることができてしまったのだろう。 それがどんなに重要な事なのかは到底想像もつかなかった。 けれど、しんらの笑顔を見ると、少なくとも見えてよかったと思えてしまう。 「ところで、描いたものが生命を持つなら、うかつに何にも描けないんじゃ?」 「うーん。右手で描く分には平気なんだ。……けど、今はちょっと無理かもね……」 包帯の巻かれた右手を掲げ、頭をぽりぽり描きながら苦笑する。 「……た、大変だね……」 どれほど大変なのか、には知る由もなかったが、自覚のない感覚を抑えておくのは骨の折れる事なんじゃないかと思う。 他人事のような言葉しか返せなかったが、出来るだけしんらに負担がかからないように力になりたい。 冷めてぬるくなってしまったお茶をあおった。 |
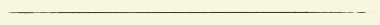
やばそうな材料色々ぶち込んだんでしょう。相手が「カレー」を知らないのをいい事に
←back next→