
さわらぬものたち
大きくても、やはりそれなりに古い屋敷なのだろうか。 廊下を踏みしめれば、ギシリ、と、年季の入ったいかめしい音を立てる。 「そこはさっきも言いましたよね。厨で……こっちの角を曲がって少し行った所が厠になりますから。 あ、こっちですよ。少し暗いから気を付けて下さい」 電気のない廊下は、昼間と言えども日の光が届かず薄暗い。 けれど、梁の上や天井の陰に、ぼんやりと仄明るい光があった。 (あれは……あ、あそこにも) 羽も持たないのに、ゆらりと、中空に静かに浮いている。おそらく、さっき山中で見かけたムカデもどきと同じようなもの。 それらは、家に入ってからも形は違えど所々でぽつぽつと見かけたが、しんらは気にした様子を見せない。 はそういうものなのだろう、もしくは、疲れからくる幻覚かもしれないと、無難に自己完結した。 充分おかしな事ばかりで、一々突っ込んでいたらきりが無いという感情も生まれ始めている。 多分感覚が麻痺してきているんだろうな、と自覚して心の中で苦笑を漏らした。 「すごく広い家ですね……本当に、一人で?」 不可解な事はさて置いて、先を歩きながらどこか楽しそうに案内をしてくれている少年に声をかける。 ひんやりとさえ感じる家の中の静まり返った空気は、一人に対してのその広さ故だろう。 狭いとまでは言わないが、それなりの広さしか馴染みのないにとって、大きい家は憧れだったが 目の当たりにしてみると、そう羨ましいものでもなかった。 「ええ……4年前にばぁちゃ……祖母が亡くなってからは」 「あ……ごめんなさい」 気まずい答えに思わず俯くに対し、しんらは首を横に振る。 「気を遣っていただかなくて平気ですよ。何とかひとりでやってますし」 こんな体たらくですけどね、と苦笑しながら包帯を巻いた右腕を指す。 沈んでしまった空気は本意ではない、と、殊更明るく振舞うしんらに合わせて、も笑む事にした。 前を向いていたのだからよそ見をしていた、というわけではないけれど、しんらに気をとられていて。 がんっ ダァン!という痛々しい音と「あがっ!」という悲鳴は同時だった。 「だっ、大丈夫ですか!?もう、だから気を付けてって……何だか、よく躓いたり転んだりしてますよね、さんって…」 相変わらずのおぼつかない足は、この昔造りの、バリアフリーの欠片もない家屋の中での油断を許さなかった。 自然の恵みをそのまんま家にしましたとでも言うかの如く、その古さも相まって、敷居や所々の段差に 理不尽なまでの凹凸がある。今回は廊下の繋ぎ目に足先を思いっきり引っ掛けたので強打した親指から中指が痛い。 勿論一番痛いのは顎だが。もう少し鼻が高ければ確実に鼻血を垂らしていた事だろう。 「ごめんなさい、お恥ずかしい所を……ここずっと、調子がおかしくて」 仮にも自分は立派な大人で、落ちてばかりとはいえ社会人として活躍していくべき人間なのにも関わらず、 至るところでドジをかましては、こうして子供に手を貸してもらっているなど、情けなさ過ぎる。 (まあ……迂闊で不注意ってところは認めざるをえないけどね……) 涙目で足と顎をさすり、受身すら取れなかった鈍臭さを悔いながら、立ち上がった。 「うん、この部屋なら日当たりもいいし……ここで構いませんか?」 障子を開けて空気を入れ替えながら、しんらはを振り返った。 夜空の下、雨や獣を恐れずに済むのなら軒下でも構わないと考えているにとっては充分過ぎる程だ。 開け放たれた障子の外には、整然として洗練された、とは言えないけれど、息づく生命と濃い緑の庭を堪能出来る。 木のぬくもりと、古い畳の発する自然の香りが交じり合ったにおいは、現代日本じゃそうありつけるものじゃない。 古風な旅館のような部屋を目の当たりにして、転がり込んだ分際としては本当に申し訳なく思う程である。 嬉しそうなの様子を肯定と受け取り、しんらが襖に手をかける。 「日が出ているうちに蒲団を少し外に出しておきましょうか」 そう言って引き戸が開いたその瞬間に、の心臓は跳び上がった。 「い、いい五百蔵さんッ!?」 暗がりに群がっていた“それら”が、光に晒された途端に一斉に飛び出してしんらに絡みつく。 夥しい数の、淡く発光するミミズのような、まさに“異形のモノ”だった。 逃げ惑うように飛び出した拍子にしんらの体にぶつかり、そこを這い回る。 普通なら悲鳴を上げそうなものなのに、対してしんらの方は少しだけ鬱陶しそうな素振りを見せたのみで、発光ミミズが 体にくっついているというのに構わず蒲団に手を伸ばそうとしている。 「ん、」 「ちょっ……大丈夫なんですか!?な、な、何これ……!?」 およそ散ってはいったが、まだ着物にひっかかって蠢いている発光ミミズを、しんらの着物をつかんで引き寄せて払う。 けれども、のひどく慌てた様子を見て、当のしんらは可笑しそうに笑った。 「あはは……大丈夫ですよ。こいつらは暗い場所が好きなやつで、影にたむろってるんです。害は無いですから」 平気なのには安心したが、しんらのその発言を受けて、眉根を寄せてしばし固まる。 てっきり幻覚か何かかとさえ思っていたのに、やはりあの「へんなもの」は同じようにしんらにも見えているらしい。 「そうそう、この間も夜中に厠から戻る途中に灯りが消えちゃって、こいつらのお陰で………って」 訝しく思って黙っている此方に構わず続けていたしんらだったが、そのうちに向こうも、はたと止まった。 「さんにも……見えてるの……?」 「え……あ、はぁ……」 「見えるの?本当に?光るミミズみたいなのや、ムカデみたいなのや……!?」 腕に縋り付いてくる程驚いた様子のしんらに迫られて、半ば退き気味に身を反らせながらも、頷く。 「いや、その、さっき初めて見かけたばかり……だけど」 「じゃ、じゃあアレ。あの、傘みたいな、ふわふわ浮いてて、足のあるヤツは見えてる?」 しんらが興奮して指差す方向に視線を向ければ、窓の外にクラゲのようなモノが浮遊している。 「え……うわっ、何ですかあれ」 「じゃあこれ、この小さいのも見えるの?」 の反応をみて、益々声を弾ませながら、今度は部屋の隅に屈みこんで手招きする。 嬉しそうなしんらとは正反対に、半ばあんまりいい予感を抱けずに覗き込むと、 花のような形の、けれども足がついていて、それらをちみちみと蠢かせるよく解らないモノが2、3匹。 もいい加減に辟易した。 いくらしんらが平気そうにそれらを見ているとしても、にとっては見た事のない、いわば正体不明の生命体である。 不気味なことこの上ない。 「……はい、見えてます……けど」 結局これらは何なんだろう。何がどうなって、こんな生き物がこの世にいるんだろう。 ここまで不可解な状況に陥ったのは初めてで、認めかけているあたり、自分で思う以上に精神がやられているのかも。 第一、有り得ないモノなど、前を浮遊する着物の少女だけで充分だ。 けれど、こうしてここで、唯一会うことのできた人間と、見えているモノが同じだという事は。 その異形達を、自分だけが妄想している幻だなどと、信じられないなどと言っているわけには行かない。 有り得ないそれらの風体だが、取り合えず幻覚というカテゴリに無理矢理収めていたのを改めなければならない。 「………そっか、見えてるんだ。初めてだよ、僕以外に見える人に会うの。………アレらは、幻じゃないんだよね」 心底嬉しそうに、しんらは微笑んだ。 彼の方も、自分以外の見える人間に出会った事で、異形達の存在を確証することが出来たようだ。 その事による感情の動きは、とは逆だったようだけれど。 愛しそうに、彼が見るものたち。 普通の人間には、見えないものたち。 多くの、およそ遠い異形のものたち。 これらは廉子の言っていた“蟲”なのだろうか。 そうだとするのならば、自分が遠い――――とんでもなく遠い場所、それこそどんなに歩いても、いくつも海を渡っても、 けして帰る事が出来ないような場所に来てしまったような気がして、足がすくむ。 現実的に考えて、ここが日本であるのは間違いないはずなのに、その何処にも、ここは当て嵌まらない気がした。 けれど、がどう捉えようとも、お構いなしにソレらは生きていて、存在する命なのだ。 彼らはそれ自体が、決して非現実的なモノなどではなく。 ――――そうだと思えると、の目には、木漏れ日に照らし出されたその部屋も、屋敷も、木々も、山も、よく見えた。 そこは、人とも獣ともつかぬ命に満ち溢れていた。 あるいは、全ては、まだ覚めぬ夢なのかもしれない―――― |
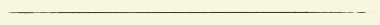
しんら夢…?
←back next→