
木漏れ日の庵
「ここが、私の家だよ」 穏やかでいて、生命力に溢れた木々に囲まれた中、たった一軒だけれども、大きな家があった。 上がった息を整え、服についた木の葉や土を叩き落としながら見上げる。何とも立派な屋敷だった。 「ここには、五百蔵しんらという子が一人で暮らしてる」 今さっき、廉子はここが自分の家だと言わなかったか? その言葉に違和を覚えて口に出そうとしたよりも早く、廉子が続けた。 「……しんらには私が見えていないからな。私の事を言っても無駄だよ。 まぁ、困ってる人を放っておくような子じゃないから、たずねてみるといい」 「見えていない」と言った時、廉子が諦めたような、少し悲しみを含んだような表情をしたように見えたのは 気のせいだったのだろうか。見えるか、見えないか。思い返せば、決まってこの話題の時は、廉子は寂しげな貌をする。 自覚がないのか、構う事無く勝手口の方へ裸足の足を進める。 そして、木で出来た戸の目の前で一旦足を止め、の方を振り返ると、息をつき、改めるように言葉を発した。 「入る前に、言っておきたい事がある。」 真剣な表情に、も思わず背筋を伸ばし、その場で畏まる。 「お前がどこの里の者かは知らんが、ここの事は絶対に他言しないと約束して欲しい。絶対に、だ」 有無を言わせぬその様子に、口の中に余った唾をごくりと飲み込んだ。 確かに、こんな不思議な体験を胸の内に留めておくのは勿体無いし、釘を刺されなければ家族や親しい人達に ふれていたかもしれない。けれども廉子は普通は見えないものだと言うし、ここまで厳しく言うからには それなりに深刻な事情があるからだろう。まあ言ったところで鼻で笑われそうな話になってしまいそうだが。 「……わかりました」 が頷くのを見届けると、廉子はまたふわりと浮き上がり、先に行っていると言い残して 庵の方へ飛んでいってしまった。 ちょっと心細いな、と思いつつ、入り口に手をかけ、「失礼します」と言って木戸を押した。 きい、と古い木が軋む音に誘われると、苔に覆われた庭石がてんてんと庵のほうへ導くように続いている。 外観よりも、庭も、建物も大きくて広い。 廉子が「子」と言っていたのだから、この家の主は子供だろうか。 どうしてこんな山奥の立派な屋敷に、子供だけで住んでいるのだろう。 人の家の敷地を、今の所はその人の許可なしに歩いているという事に、緊張してしまう。 (それにしても、すごいな……そこらへんの観光名所より綺麗かも…) 隙間を縫って差し込む陽光が、濃い緑に染められて優しく降り注いでいる。 気を失う前は木枯らしの中、身を縮こまらせて歩いていたが、ここは寧ろ夏のように暑くて、 脱いだコートやマフラーが邪魔な位だ。 「…っと…!」 また。何もないのに転びかけた。 さっきから、歩き始めてからずっとこんな調子で、身体のいたるところに違和感がある。 もう腰が抜けているというわけでもないだろうに、大荷物だからだろうか?変な体勢で気絶していたから? 加えて、意識ははっきりしているはずなのに、思考はどこかボンヤリしていて今ひとつすっきりしない。 小さな凹凸にもつまづかないように必死だった。実際、ここに来るまでに5回ほど見事に転んでいる。 (うわ、子供の時以来かも、こんな風に転ぶのって)と、転倒した事に対して素直な感動を覚えたのは最初だけで、 5回目にもなると廉子の温度の低い、呆れを含んだ眼差しを避けるのに精一杯だ。体も痛いし。 どうしたことだろう。自分はここまで鈍くさい類に入るという事はなかった筈なのに。 (体育の授業で勢い余ってすっ転んで大恥かいて以来、じゅうぶん気をつけてるつもりなんだけどな……) 一日のうちに、しかもこんなに短い間隔でドジを踏むなんて異常事態だ。 ぎくしゃくとした体の動きに、慎重に気をまわしていないと足を滑らせそうになる。 (生まれて間もない馬とか鹿が立って歩くのって、こんな感じなのかも) どこかズレていると自分でも感じるような事を考えていると。 「……あれ?お客さん?」 「!?」 例えるなら、めいっぱい引っ張りに引っ張っていた緊張という名の糸の真ん中に、 勢いよくカッターを振り下ろしたというのが適当だったろう。 「めずらし…」 「ぶへぇ!」 「…ぇえッ!?」 およそ乙女(という年でもないが)から遠しと思われる呻きをあげて、側面から滑りこける。 この家に実質住んでいるのが一人だけというなら、縁側に腰を下ろしていたこの少年が「五百蔵しんら」だろう。 しんらは声を掛けた拍子に転倒したに驚いたが、慌ててこちらに駆け寄って来てくれた。 「だ、大丈夫ですか!?すみません、驚かせちゃって……」 「い、いやいや……気をつけて無かった私が悪いんです。本当に申し訳ない……」 名前からは推察できなかったが、男の子だったのか。 黒い髪に、同じく黒い利発そうな輝きを宿す瞳。年齢に似つかわしくない落ち着いた色味の着物を着ている。 顔立ちは違うけれど、どこか廉子と似ているような気がした。 予想どおり、しんらはまだあどけなさを残す外見だったが、その物腰から弱冠大人びているように見えた。 まさか初対面でいきなりの痴態を晒してしまうとは。しかも年下の少年に心配されてしまうとは。 赤くなった顔を、できるだけ見られないようにしながら、差し伸べられた手の好意に甘えて立ち上がる。 「あの、は、初めまして。……という者なんですけど…」 「えっ、……、さん?“ギンコ”さんじゃなくて?」 名前を聞いて不思議そうな顔をしたしんらは、を他の人物だと思い込んでいたらしく、首を傾げて聞き返した。 「…ギン…?」 ―――――銀の、色の… ――――――「銀蟲と、呼んでいる」… 無いはずの記憶が、断片的によぎった。 「……“ギンコ”さんって?」 考えるが早いか、殆ど弾みで聞いてしまっていた。ただの、知らない筈の記憶、 誰かが呟くのが、ほんの短いシーンが、頭の中に残っている。 小さな鈴を一振りだけ、鳴らすように。 目覚めてから何もかもが見たことのないものばかりの中で、それだけは自分の中に確かにある記憶。 聞かずにはいられなかった。 「えっ?……だから、蟲師のギンコさん、ですけど……違うんですよね? すみません、此処に来客なんて滅多にないものですから、文を貰ったし、てっきり…」 蟲師。また聞かない言葉だ。 職業を指す名前だろうか。廉子の話と組み合わせると、蟲に関わりがあるのだと思われる。霊媒師みたいなものか。 (……人の、名前だよね……じゃあ違うのかな…) 誰かが呟く他は、銀色の何かが泳いでいるようなシーンの記憶しかない。 それも、人とは言えない“何か”が。 「えーと……さん、でしたよね。僕は、五百蔵しんらといいます。さんは商人の方、なんですか?」 転んだ拍子にぶちまけた多くの物達を見てしんらはそう判断したのだろう。 美しい庭がすっかり散らかってしまった様を見て、は大いに慌てた。 「うわっ、ごめんなさい! いえ、私、商人じゃないんですけど……直ぐに、片付けますから!」 焦って荷物を掻き集めるの様子に、しんらは気を悪くした風もなく、むしろ楽しそうに笑みを浮かべた。 「……はい、どうぞ」 勝手が解らないので戸惑ったが、基本的にお茶なら文化圏や時代水準が違っても煎れ方は変わらない。 しんらに湯飲みを渡したは、さっきと同じように縁側に座る彼の横に腰を下ろし、自分の分の茶を脇に置く。 「ありがとうございます。……すみません、お客さんなのに、お茶なんか煎れさせてしまって……」 申し訳なさそうに軽く頭を下げるしんらに、こそ申し訳ない、と、慌てて手をふった。 「いえいえ。そんな大層な者じゃないですし、それに手に怪我されてるのに荷物片付けるの手伝ってもらっちゃって」 しんらの右手には包帯が巻かれている。指を怪我しただけだと本人は言ったが、 それでは日常生活においては色々と不便な事もあるだろう。 「それで、話は戻りますけど……さんはどういったご用件でここへ?」 「…用件……とか、そういったものではないんですけど、ええと…」 そこで言葉を切ってお茶で口内を潤す。 「おかしな事を言いますが」と前置いて、今までのことを話し出した。まぁ、そんなに長いことはない。 一応廉子の事は伏せておいて、状況の説明とあと、いくつかの質問もした。 連絡を取ることが可能そうなあらゆる手段、交通機関や警察の事、地名も聞いてはみたが、 廉子と同じように、しんらにもその全てに心当たりがないようだった。 はだんだんと奇妙な気分が湧いてくるのを感じた。 こんなにも大きな屋敷なのに、鉄筋やコンクリートなどを一切使わずに自然のものだけで築造されている。 廉子もそうだったが、目の前のしんらも着物なんて珍しいものを普段着として着用している。 文明の利器は勿論、現在使われている多くの事物に関する言葉が全く通じない。 まだ二人だけなのだから確証に至るには早すぎるが、は有り得ない可能性を感じずにはいられなかった。 (まるで、タイムスリップでもしちゃったみたい……) しかも、“蟲”という存在が、その事を更に非現実的にしている。 タイムスリップというよりも、異世界に来てしまったような。 そうだとするならば連絡を取れないどころか、下手をすれば――――… 「大丈夫、ですか?」 「……え…?」 どんな顔をしていたのだろう。 いつの間にか俯いていた顔を上げると、ひどく心配そうなしんらの顔が覗き込んでいた。 大丈夫、と、動揺しているためか隠しきれてなかった虚勢を滲ませた顔を見て、それでもしんらは笑ってくれた。 「……そうですか。もしかしたらさんは、とても遠い所に住んでいたのかもしれませんね。 どうしてここにいたのかは、僕にも解りませんが…」 そこで言葉を濁すと、口元に手を置き、うーん、と考える仕草をとる。 しんらとしては、いきなりここにいればいいなんて無責任な事は言えないし、かといって帰そうにも連絡手段も方法も、 あげく場所すら知らなければ放り出すのと一緒だろう。 にしてみても、後に続く言葉が何であるのか想像もつかないし、逆の立場になったとしても なんと言って結論を導き出せばいいのか解らない。 「麓までは遠いんですか?」 「え……あー…はい。結構ここって山奥だから…」 とにかく、こう山のど真ん中じゃどうにも出来ない。 自分ときたらあまりにも軽装だし、食料を持っているとはいえ日持ちのするようなものじゃない。 旅慣れていないから方向感覚も心許なく、誰かと一緒でなければ山を降りるまでにくたばる可能性があまりにも高い。 「すみません……僕は此処を離れるわけにはいかなくて……」 「あ、そ、そんな。いいんです。さすがにそこまでお世話になる訳にはいきませんから……」 とはいえ、にとって頼れる者は今の所しんらしかいないというのが現状である。 確かに麓まで送ってもらうなんて、図々しいにも程があるだろうが、一人で山を降りるのも不可能というなら が雨露をしのげるかどうかもしんらに懸かっているのである。 廉子の言うとおり、この少年は目の前で困っている他人を放っておけないようで、 突然訪ねてきたの身の振り方を真剣になって考えてくれている。 自分よりもかなり年下の少年にこんな事をさせるのを、はどうしようも無いほど申し訳なく思った。 程なくして眉間の皺を消して、しんらは顔を上げる。 「うーん……ま、これからの事は後で考えましょう。突然の事でさんも大変だったでしょうし、 今日の所はここでゆっくりして下さい。何なら暫く居て下さって構いませんから」 楽天的に、にっこりと笑うしんらに、は目を瞠った。 「い、いいんですか? 自分で言うのもなんだけど、気が付いたら此処に居た……なんて、怪しい事言ってるのに……」 普通に考えて、何か別の魂胆があるのか疑っても当然なくらいだ。 しかも廉子に念を押されたように、ここの事は他言できないような事情があるだろうに、 こんなにあっさりしていていいのだろうか。 こちらにとっては全部事実だと言えども、どう考えても奇妙な事を言う自分を否定しない少年に感謝の念も湧くが、 同時に何か騙されているのではないかという疑心や、こんなに素直で大丈夫なのかと心配の念を抱かずにはいられない。 そんなの意を汲んだのか、しんらは安心させるように言う。 「はい。僕は結構、こういう事には慣れてますから。何しろ自分の……っと」 言葉の途中で、いたずらをしたのを危うく自分で親に告げそうになった子供のように、手で口を諌める。 「……五百蔵さん、の?」 「あ、な、何でもないです!そう、それよりも、部屋を用意しますね!広い家ですから、遠慮はしないで下さい!」 首を傾げるに対して言い繕うように捲くし立てると、空になった湯飲みを持って立ち上がる。 腑に落ちない部分を残しつつも、しんらに従って、五百蔵家にお邪魔することにした。 |
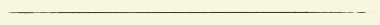
しんら登場。
←back next→