
樹海に遊ぶ童女
ゆったりと、流される。 何かが、うねる。 「蟲だ」 ムシ? 銀の、色の 「銀蟲と呼んでいる」 ギンコ……? 「何だこいつ?妙なヤツ……」 枕元に、誰とも判別のつかない声を聞いて、ゆるゆると覚醒に近づく。 「枕元」といっても、肝心の枕はいつになく頭の下に敷かれてはいないようだった。 顔の表面がカピカピする。洗顔せずに寝たのだっけ?まるで海水に塗れた後乾いたような、べたべたとした不快感がある。 瞼のわずかな隙間が光を受け入れていくにつれ、自分が珍しくうつ伏せになって寝ている事も解ってきた。 これほどの寝相を発揮するなんて、よほど疲れていたのだろうか?昨日は何をしていたんだっけ? と、その記憶を呼び覚まそうとして、重たげなまどろみの中、ぼんやりと考えた。 けれど、霞がかった思考をどれだけ整理しようとも、昨日寝床に入るまでにしていた事が思い当たらない。 取り敢えず大雑把な所から思い出していく事にしよう。まずは昨日の夕食から。 (…………………て、……あれ?) そこまでボケていていいのだろうか。これでもまだ20代前半もいい所なのに。 気を取り直してもう少し前の事を思い出してみよう。 そうだ。昨日は普通の平日だった。だから大学へ行った事は覚えている。 授業の内容など殆ど覚えてはいないが、取り敢えず2限を受けて、昼食をとって。 (…そう、そう…よね。お昼は確かサンドイッチ食べて……) 食堂が混んでいたから、購買部で買ったのだ。それから、3限と4限を受けて、その日の時間割は終了。 (えーと……あ、そうだ、買い物したんだった) 普段と違う事をしたから、覚えている。いつもはまっすぐ家まで帰るのだが、この日は月に一度のセールの日。 安い時ににまとめ買いをしておいた方が、後々家計の助けになる。 家族の中で買い物に出るのは専ら自分しかいないので、この期に一気に調達しておくのが恒例となっている。 食材は勿論、常備薬の補充や日用雑貨などなど、締めれば結構と言わず、かなりの大荷物になる。 恐らくこんな大荷物を鼻息荒く運んでいる女が、花も盛りの女子大生だとは誰も思うまい。 などと自棄的な笑みを浮かべて、大学の友人知人に遭遇しない事を祈りながら帰ったのだっけ。 疲れる事をしたというのなら、この事以上に思い当たる事はない。 だが。 (……ちょっと、まって…?) そう、此処までは順風満帆と思い出してきたのだが、やはり家へ帰り着いてからの記憶がない。 それどころか、家へ到着するまでの記憶が、ふっつりと消えてしまっている。 「………………うわあぁあ…!?」 その時の事を思い出して、体中の血が、一斉に逆戻りしたような感覚に襲われた。 そう、確か、自分は家に帰り着いていない。それどころか、あの時。 体が、殴られたとも電気ショックを受けたともいえるような感覚に突然襲われ、初めて気絶という体験をしてしまった。 記憶がないのは当たり前だ。枕がないのは当たり前だ。あの時から今この瞬間は繋がっている。 だとしたら、ここは家、ましてや寝床などでは到底有り得るはずがない。 がばぁ、という擬音語がつきそうな勢いで、まどろんだ体勢から一気に身をおこしたので、軽く眩暈に襲われる。 「わっ!?……い、いきなり何だ!?」 「!?」 そして、目の前で驚いて仰け反る存在に気付いた。 艶のある黒髪をおかっぱ頭に整えた、可愛らしい振袖姿の人形……のような女の子だった。 この子が先程枕元、いや、頭上で何事かを呟いていた張本人だろうか?今日は七五三の日だっけ。 だがその子に構っていられる余裕などない。 今はとにかく状況把握だ。 「な……ここ、どこ…!?」 記憶の最後には、自分は住宅街を歩いていたはず。だが、ここは。 嫌な予感がざわざわと高まってくる。 まさか、とは思うが。気絶させられて、車に乗せられて…? きょろきょろと、360°見回してみても、木、木、木。茂み、茂み、茂み。 余りの緑の濃さに、頭がくらくらする程だった。 空気は澄んでいて、つんと枝葉のにおいが鼻をつく。 緑化された公園やそこら辺の林に生えているような木とはまるで違う。 あるものの幹はどっしりとしていて、生命力に満ち溢れていて。原生林、という言葉が頭に浮かんだ。 それほどに深い山奥に連れてこられたのだろうか?いったいどれくらい遠い場所に連れて来られたのだろう。 テレビで見た光景と似ているが、まさか青木が原じゃないだろうなと考えつつ、近くにそのまんま転がっている 荷物の確認をする。一番心配だった財布は無事だった。もともと買い物帰りで余り入ってはいなかったが。 定期券も、学生証も、家の鍵も、あの購入物の山も。確認したが、全て無事。 本当に、あの時気絶してそのまんま、場所だけが変わっているだけという状態でそこに在る。 人為的なものだとしたら目的は一体なんだったのだろう。まずないとは思いつつも、衣服の乱れはチェックしてみた。 肌寒さも増してきた季節、着ていたコートに、マフラーも健在。予想通りなんともない。身体に欠損部分や損傷も無し。 まあ、自分の身体が狙われるとしたら、世も末だよな、とほっと息をつく。 一応状況を現実的に並べてみると、こうだ。 帰り道に襲われて、拉致されて、どこかの山奥に捨て置かれた。 「頭でも打ったのか?何でこんなところにいる?」 そして多分この目の前の、見かけによらずちょっと口調のキツイ女の子は、誘拐仲間だと思われる。 両家族への身代金の要求は終わったのだろうか。お互い捨て置かれるなんて。 とまぁ、こんな具合になる。 あまりにも非日常的ではあるが、あくまでも現実的に考えた結果である。 そうでなければ、いや、そうとしか説明がつかない。 何故に自分は世界遺産に登録されそうな勢いの森に取り囲まれているのか。 何故にそんな所に着物を着た少女がいるのか。 多少ミスマッチな所は、そうして無視して強引に押し通せば、おかしな事はない。認めざらざる状況ではあるが。 ところが、現状はそんなに現実的なものじゃないと、少女の口ぶりは示していた。 「何なんだこいつは……本当に変なニンゲンだな……」 はた、と、は思わず動きを止める。 やっぱり、変だ。変な気がする。少女の口から出た言葉は、の仮説とはあんまり合致しない。 向こうはこの大自然というフィールドに、少しの疑問も抱いていない。 むしろここを自分の居場所としているようで。 けれど、鬱蒼とした森の中、裸足で着物の少女が徘徊している、だなんて。 しかも、自分だってヒトと変わらない姿をしているくせに、少女が言った「ニンゲン」という響きは、まるでそれが 自らとは違う存在を指しているかのようで。 さぁ、と顔から血の気が引くのが解った。 (も、もしかして、これが世に言う……えーっと…) 固まって、冷汗を湛えた青い顔で、じぃっと食い入るかのような視線を投げかけるに気付いて、 少女はいささか驚いたように目を丸く見開いてみせた。 「ん…? まさかお前……私が見えてるのか?」 「みっ、みみみ……見えてるって、やっぱり、その、そういうアレなんですか!?」 幽霊。俗に言う成仏していない人々であると証明するかのごとく台詞に相違ない。 どうとっても、生きた人間の発言とはとれないものである。 「……そうか、見えるか。……お前はよほど強い妖質を持った人間なのだろうな。あの子にさえ、私は見えないのに…」 驚き慄いてパニックを起こしているを他所に、少女は少しだけ顔を伏せて呟いていた。 聞きなれない単語も、人名らしき言葉も、の耳には入ってきたが、それらに考えを回す余裕などない。 未知との遭遇に、とにかく早く、この非現実が過ぎ去ってくれるように祈った。 こういう場合、とっさにどうすればいいのだろう。素人が下手な退魔法を使うと かえって悪化する、と、夏の怪奇特番で霊能者の人が言っていた気がする。 (と、と、とにかく気持ちが大事だ……心を強く持てばきっと大丈夫…) 「……何をしてる」 手をすり合わせて、ナンマイダナンマイダとぶつぶつ言い出したの方へ、 少女は不審そうな、呆れたような視線を向ける。 「うう……効いてない…」 がくりと肩を落として、次にはあまりよく覚えていない般若信教を試そうかと意気込むに、 やれやれといった風に少女は溜息をついた。 「無駄だぞ。私はそういった類のもんじゃないからな」 え、と呆けるから視線を外すと、少女はまた少しだけ俯き、嘲笑ともとれる微笑を浮かべた。 「まァ……似たようなものもんかもしれないな。人でも、蟲でもない私は……」 「……ムシ…?」 幽霊ではない、と言うからも安心かけたしたが、今度は「人ではない」と少女が言い出したのに、再び身を硬くする。 そうして、独り言ともとれる少女の言葉を、聞き返すように反芻した。 およそ人とはかけ離れたもの達。目の前の少女は、どう見ても人の形をしていて、どこをとっても あの草むらや空中を飛び回る節足動物とは関係などなさそうに見える。 また、それらとは違った印象の響きを、その言葉からは感じた。 人じゃないと彼女は言うけれど、先程から笑ったり悲しそうにしたり、こんなに感情が豊かなのに。 けれど、どこか、幻めいた印象も感ぜられて。 「ふふ……聞かない名か?私が見えるくらいだ、これまでにも多くの異形のモノ達を見ただろう」 「いぎょう……って…」 そんなの、常軌を逸脱した現象を見るのなんてごめんだと言いたいのに、言葉を失った口では続けられない。 「―――――アレらは、"蟲"と呼ばれるモノだ」 普通の人には見えないが、幽霊などと違ってこの世に確かに存在しているもの。 我々と同じく生きていて、けれど、その根源に最も近しいもの。 少女の説明に、わけが解らない、と、言葉にせずとも伝わりそうな顔をは自分でもしているだろうと思った。 ようするに“蟲”とは、幽霊に近いけど、一応、一種の生物という事か? それでも、人には見えないモノである限り、それらは人とは相容れられる事無く、 理解されないという点では、幽霊などと大差ない。 そういった答えを導きだすのも、あながち間違ってはいないのだろう、と、は考えた。 しかし、少女が今言ったように「多くの異形のモノ達を見ただろう」という問いには肯定できたものではない。 だいたい、霊感を始めそういった生来の才からことごとく見放された自分が、 存在してはいるといった時点で現実的とは言えど“蟲を視る能力”といった特別な力など持っているはずがない。 その証拠に、科学的に説明のつかない奇妙なものに出遭ったのは、この少女が生まれて初めてである。 21年も生きてきて、“蟲”という存在があるなんて、何処へいっても聞いたことがない。 “妖怪”や“精霊”の類を、そう呼ぶ地域なのか。それとも、新しいカテゴリに相当するものなのか。 どちらかと言うと後者のような気がする……が、それは兎も角。 「あの……話は戻りますけど、ここって、何処なんですか?…東京はどっち?この樹海っぷりは青木ヶ原ですか? …それともどこか別の県の山中?」 ごちゃごちゃと考えはしたが、そんな事はこれから先に大して干渉してくるような事ではない。 とにかく今は帰らなければならないのである。 見上げれば、葉の隙間から覗く日は真上よりも少しだけ傾きかけている。 帰途についていたのは、日も沈んだ薄暗闇の中だったから、最低でも、この山中で一夜明かした事になる。 連絡も無く、帰らなかったのだから、余程家族は心配しているだろう。 ところが、の言葉を聞いて、今度は少女が目を丸くして不思議そうに首を傾げた。 「……トウ、キョウ?アオキ……? どこの里の者なんだお前?だいたい、どうしてこんな所まで来たんだ」 「里って……や、やだな、東京ですよ、東京都。首都だし、知ってるでしょう?どうしてあなたもここに?」 何かの冗談か。「東京」も通じないほど閉鎖的な場所なのだろうか。閉鎖的というか、未踏の地って感じだけど。 「さあ、知らないな。ここから離れた事がないし……私はこの近くの家に、ずっと前から暮らしているから」 家があるという少女の言葉に、の目が活気を取り戻した。 少女の家で、もしくは人が住んでいる場所があるのなら、どこかで電話を借りられるだろう。 一刻も早く自分が無事であるという旨を家族に伝えたい。 「あっ、じゃあちょっと電話を貸してもらえませんか?……私、気が付いたらここにいて…家に連絡したいので」 「………デ…ンワ?」 またも、いかにも今まで一度も発音した事がなさそうに、少女がの言葉を繰り返す。 「………………ま……まさかとは思うけど…電話って…ない?」 冷汗をたたえて問うてみるに、少女は一刀のもとに斬り棄てる。 「知らんな」 万事休すと言わんばかりに、がくり、と膝を折り両手を地面につけて項垂れる。 どれだけ田舎だと言うのだろう、ここは。 「なんだ、帰れないのか?」 「だから、来ようと思って来たわけじゃないし……こんな深い森見たこともなくて…」 帰ろうにも、どっちの方向へ行けばいいのやら、検討もつかない。 下手をすれば、いや、絶対に遭難する事は目に見えている。 そんな場所で、人間と言わずとも言葉の通じる存在と出会えたのは、とんでもなく幸運だったのかもしれない。 ほとほと困り果てて動けずにいるを見て、少女は溜息をついた。 「間抜けなニンゲンもいたもんだ。……あっちの方に行けば、下りの道みたいなのがある。 記憶が正しければ、確か一山越えた所に里があった筈だ。日の暮れないうちにお帰り」 そう言って、ばつの悪そうな表情を此方から背け、背を向けようとした少女の着物の袖を掴む。 きっと相手にとっては迷惑だったろうし、普段ならばそんな事しようなんて思わないけれど、状況が状況だ。 「待って! そんな……私、こんな場所でどうしていいか……」 どんなに目を凝らしても深い木々が入り組んでいるばかりに見えて、その先に一人で進む勇気なんて無かった。 一山越えるなんて、どれほど行けば次に人のいる場所に出られるどうか、見当もつかない。 もしも電灯一つ無いこんな場所にひとりきりで、日が暮れてしまったら。考えただけで恐ろしい。 少女は暫く渋い顔をして思巡していたようだったが、とうとうもう一度深い息をついて、袖を離すように促し、言った。 「………しかたないな…こっちにおいで」 そうして、ふわりと宙へ浮き上がった。それを見て、勿論は仰天する。 話に聞いていたとはいえ全て信じたわけではないし、やはり人の姿でいきなり飛ばれると奇怪な光景に思えた。 目を剥いているの方を横目で見てクスリと笑うと、少女はそのまま浮遊してある方向へと向かう。 呪縛から開放されたは、ちらばった荷物を大急ぎで掻き集めると、勢い勇んで立ち上がった。 そのまま、駆け出そうと一歩踏み出したが。 「わっ!ぎゃあっ!?」 「……何をしてるんだい」 どうにも踏みしめようとした足に上手く力が入らずに、派手にすっ転ぶ。 転んだ鼻の先に、半透明のムカデに似た「何か」が地面より少し上を這っていたので、悲鳴に悲鳴を重ねた。 見事な転倒ぶりを見て、呆れを通り越した感心を表情に浮かべた少女が浮きながら覗き込んできた。 「わ、わかんな……か、から、体にっ、上手く力が入らなくて……それより何か変なものが!」 ぶるぶると震える指先で、さかさかと逃げていくムカデもどきを指すが、少女はさして興味を示さず眉間の皺を濃くした。 「はぁ、何を今更。そんなもの、そこら辺に普通にいるだろうに。ぐずぐずしてると置いていくからね」 いや、いない!普通にいないから!とツッコミたくて口をパクパクさせる此方に構わず、再びとん、と裸足の足を 地面に打ち付けて少女は浮かび上がる。 「ああっ、待って!い、今行きますから!」 兎に角、折角付いて行ってもいいという許しを貰えたのに置いていかれては堪らない、と変なモノは無視して起き上がる。 腰でも抜けているのか、体が妙に意思と馴染まなくて、がくがくフラフラとしながら赤い着物を見失わないよう追った。 「……へぇ?ついてくるんだ。化かすかもしれないよ」 やっとその歩みに追いついたと思ったら、木の枝に戯れるように身を預けた少女からそんな一言。 必死な形相の此方を見て、意地悪そうにニヤリと口の端を妖しく吊り上げて笑みを湛えている。 「……い、いやだなあ。状況のせいもあるけど、私は信じてるんですから、やめてくださいよ…」 とは言いつつも、貼り付けた笑顔とは裏腹に、内心は冷汗だらだら状態である。 他に行く宛てもなし、この人間じゃないと言う少女について行くしか、今は取るべき道がないのである。 嘘も方便とも言うではないか。汚い考えかもしれないが、ここでこうして少女の機嫌を取っておかねば 後々身の振り方に困るというのが本音である。 心の中の恐怖心や疑心を知れば、少女の方もを信用しないだろう。 もっとも、少女が本当に化かそうと思っていなければの話だが。 幸い、本心を知られずに済んだようで、少女は照れたように、フン、と鼻を鳴らす。 「妙なニンゲンだね……と……そうだ、お前、名前は?」 「っていうんですけど……あなたは?」 「ふぅん……。私は、廉子だよ」 口にされた変わったな響きを持つ名を、は口の中で租借した。 「……レンズ……」 やはりここまで地方になると、人名の文化も変わっているのだろうか。 もっとも、最近は名前と言えるのかと思うほど、奇妙なものも多いけれど。相手は人ではないのだから尚更か。 「えーと、廉子“さん”?“ちゃん”?」 「“さん”の方にしてよ。もう“ちゃん”なんて年でもないからね」 やはり、口調や仕草の雰囲気から、外見以外は、彼女は年を経ているようである。 どうりで、童女に対しているのに敬語がしっくりすると思った、とボンヤリ考えるに、廉子は早くおいでと声をかけて、 ふわりと一層高く飛んだ。 緑金色に霞むその光景は、にはおよそこの世のものとは思えなかった。 「この世」が「どの世」なのかも、まだ知らずにいるのに。 |
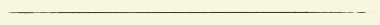
廉子と接触いたしました。
←back next→