
彼の岸のひと
真昼の位置に昇った太陽が、さんさんと、今日とそれ以前を変わらず照らしている。 立ち並ぶオフィスビルの外壁がそれを反射して、世界は文明の繁栄を誇るが如く輝いてるみたいに見える。 見える、だけ。ブラインドごしに垣間見えるそんな光景に、今だけと言わず何の感慨も感じられない。 (やっぱり私って、何にも魅力とか無いのかなあ) グループ面接会場で、横の人が活き活きと自分の事を話しているのを黙って耳に流し込みながら、ぼんやり考える。 「はい!サークルの他にもボランティア活動にも積極的に参加しておりまして、休日も……」 はきはきと滑舌良く話す隣のリクルーターの話を聞いて、目の前の面接官だけじゃなく自分まで感心してしまう。 負けじともう一人の男の子も、「私もサークルではテニス部に所属しておりまして……」とアピールを始める。 そっちの活躍ぶりも凄い。3人一組の面接の筈なのに、まるで私なんて居ないみたい。 …って、だめだ、だめだ。 私も何か言わなくちゃ。 自分で言うのもなんだけど、そんなに悪い人間じゃないと思う。 困っている人が居たら助けたいって思うし、絶対に他人に逆らったり争ったり、悪口を言ったりなんてしない。 普通の、いい人間のはず。アピールする事、何か伝えないと。 勉強……できません。運動……できません。バイト経験は……お正月に年賀状の仕分けなどを少々。 家事は両親共働きなので、結構普段からやってます。得意なのはカレーです。 ……くらい? (ああ、馬鹿みたい) みじめな気持ちになりながら、膝の上にある自分の手をじっと見ていた。 母親ゆずりの指。あ、と気付いた。 (そうだ、爪の形だけはちょっと自慢かな…) それだけだ。 当たり前だけれど、そこの会社も一次の面接で落ちてしまった。 帰ってきた家族にそれを報告をしなきゃならないのが、辛いなあ。 「ちゃんと、いいところに就職しなさい。ご近所に恥ずかしくて言えないようじゃ困るでしょ」 親は、体裁を物凄く気にする。 やっかいな事に隣の家のおばさんの子はとっても良く出来て、それを自慢されるから、 今まで頑張ってもあんまり結果のふるわなかった私は、お小言ばっかりだ。 何だっけ、ついにこの間、テレビCMでも聞いた事のある会社に内定が決まったって、誇らしげに言ってたな。 それに引き換え、取柄のない私には、就職難の今の社会は厳しくて。 「自分が何をやりたいのか」のアピールが弱いと就職支援の人には注意を受けたけど、でも。 「とにかく何でもいいから、やらせて下さい」としか言えない。どうしていいか解らないんだもの。 誰からも嫌われたくない。害を受けたくない。 おおよその人がそうして輪から外れないように生きようとしているように。 私も、「暗い子」なんて周りから言われないように、いつも必死になってる。 猫背のクセに無理して上を向いて、皆が笑っている所では面白くなくても、笑って。 そうしてたら、一人では無かったけれど、本当に相手が自分を好ましく思ってくれているのかは疑問だ。 親しげな、けれどぎこちない会話。 「たるいよね」「頑張ろうよ」「大丈夫?」「応援してるし」 社交辞令が飛び交う日常の中を、それらしく笑って過ごすけれど。 結局自身の事が、相手も自分も一番大事で、あと一歩前に歩み寄れず、家に帰ったら、大きな溜息を一番についている。 にこにことした表情で明るく話す自分こそ本心だと思い込もうとして、疲れているのを実感する。 自分の事しか解らないから、他の生きている人が同じように思っているのか知るのは不可能だけれど。 結局、こんなに空虚なままに、人生って続いていくんだろうか。 大して輝きも発しないうちに20歳を超えてしまった今も、周囲の色に染まるように生活してる。 色? そもそもこの世に色なんて感じた事なんて無い。すべては無色透明で、大した起伏も無い。 何にも不満じゃないと言えば嘘になるけど、そういうもんなのかな、とも思う。 生きていく事は、普通であり続ける事。それが一番幸せなんだって充分解っている。 漠然と思う。 きっとこの身体は「私のもの」じゃ、ない。 瞼を閉じて、世界から目を背ける。 「私」として生れなかったら、きっともっと世界に「色」を見出せただろうに。 闇が濃い。 圧倒的な黒い空間に、喰われてしまいそうな、そんな夢。 それが普段見るものとは異質だと感じたが、所詮夢でしかないとたかをくくった。 恐いと感じる自分を押し込んで、その中を歩く。 「ここ」は、夢の中だけは、私が自由にしていい世界なのだから。 何処までが「私」で、何処までが「私のものではない」かの線引きは解らなかったが、 少なくとも、確実に自分のものではない「体」を置いてきているこの場所で、 私は自由に動いていいはずだった。誰に干渉される事も、影響を受けなくてもいいのだった。 そう考えながら歩いていると、気は大きくなり、歩幅も大きくずんずん先へ進む。 ふと、何もない空間の中、五感の一つがそれを捉えた。 地鳴りのような、何かが、激しく、大きく轟く音。 何の音だろう。聞いたことがある。例えるなら、そう。大河が流れる音のよう。 この闇の中、流れは何処にあるのだろう、と視線を彷徨わせると、遥か彼方に、奇妙な光の線を見た。 迷い無く、進む。近付くにつれて音が大きくなっているので、流れているとしたら、あの光だ。 純粋な好奇心が大きく膨らむ。こんなに素直になれるのは、ここでしかありえない。 それが現実なら、気になりつつも、関係ない事だと踵を返したことだろう。 (うわぁ……凄、い…) 綺麗だという感想を持つには、目の前に広がる光景は、それも含めつつ全てを凌駕しすぎていた。 轟轟と激しい勢いで流れているのは、見たこともない光で、水とは言えなかった。 どうして、自分の深層心理だと言われるその空間で、こんな光景をお目にかかれるのかは解らない。 けれど、ただただ、圧倒され、感動する事以外にはできなかった。 ずっと、ずうっと、見ていたい。覚めることがなければいいのに。 この夢が終わる事がなければ現実に戻らなくてすむのに。酔うような感覚でそう思った。 ああ、やっぱり、それが本音なんだ。 口と頭の先っぽでは普通が一番だと言い聞かせながら、生きてきたのに。 綺麗で、壮大で、果てしなくて、少し恐くて、でも優しくて、そしてひどく懐かしい。 圧倒されるほどの、色んな感情が湧き上がる。 その激しい流れを前に、あんまりにも自分の辿ってきた道が小さくて、情けなくて、心細くて、みっともなくて。 押し込めていた自分を思い起こし、気のせいだと知りつつも、今始めてそれらを慰めて貰っているような 感覚に陥って、誰もいない所であるという事が更に拍車をかけて。 溜め込んでた感情が、涙になってこぼれた。 何とかしなきゃ。何とかしなきゃと思って必死なのに、頑張ってるのに報われない。 私がしっかりしてないから、いけないんだ。そうは思うけど、ちょっとは、自分の事を誰か気に掛けてほしい。 夢なんて、やりたい事なんて、何にも無い。 何にも持ってない、普通でしかない自分が嫌。でも、変化するのはもっと恐い――――― 小さい時に、迷子になった時みたいに、いつか忘れてしまった泣き方で。 手で拭わずにためていた分を押出すように流れる涙は、ぽたぽたと大河のほとりに落ちた。 久しぶりに高ぶった感情が、さらに自分の心を逆撫でていく。 年も忘れて、誰に気をつかうことなく、自分自身で泣いた。 どのくらい泣いたのかは解らない。もう、涙もかれ、引き攣るような嗚咽しか出せなくなった。 泣き方は落ち着いても、堰を切った感情はまだまだ昂ぶっている。 ふと、しゃくりあげながら、無意識に足を進めた。 このまま、この光の洪水に、身を委ねてしまえたら。 定まらない意識の中で、そんな事を思った。自殺願望なんて持っていない。 ただ、この美しい流れに身を任せるのが、どんなに心地いい事なのか試したくなった。 そう、この世界でなら、夢の中でなら死ぬことなんてないのだろうし。 そう思って、もう一歩足を進めた時だった。 「それ以上、近付くな」 それはもう、吃驚した。 誰もいないと思い込んでいたので、その声は予想だにしなかった。 肩を大きく揺らすくらい驚いて、狂ってしまったかのように動く心臓は痛くて。 そして、状況を驚くべき早さで客観視する自分の思考は、一気に顔に熱を昇らせた。 その声の主はここにずっといたのか。そうなると、さっきまでの見苦しい自分を全てさらけ出していたことになる。 慌てて辺りを見回すと、光の河に気をとられて全く気付かなかったが確かに、青年が一人、対岸のほとりから 少し離れた所に腰を落ち着けている。 「…っ……っ!?」 あまりにも予想外で、恥ずかしすぎて、何を、どんな言葉を発していいかも解らず、息を詰まらせた。 ここまで、おそらく真っ赤になっているだろうと自覚できる程、顔が熱く感じるのは初めてだ。 の、予想を遥かに上回ったらしい驚愕具合に、光に霞む向こう岸で青年は苦笑を浮かべた。 「なんだ、あんまり五月蝿いもんだから、てっきり子供が迷子にでもなっちまったかと思ったんだがな」 いい年したお嬢さんか。タバコを咥えた口の中で、その部分は聞こえないように言っているのが解る。 浮かべた笑みには、どこか意地の悪いものが含まれていた。 (や、やっぱり見られてたんだ…!) 嘘でもいいから、無かった事にしてほしかったのに。さっきの自分は言ってみれば素っ裸だった。 恥も外聞も女らしさも、とにかく全て捨て去った、人に決して見られてはいけない部分全開状態だった。 の羞恥心をわざと煽るような物言いは、確信犯のそれと思われる。 更には顔の温度を上げ、裸足でその場から逃げ出したい衝動にかられた。 蔑まれるのだろうか。異常な人間だと思われるのだろうか。「普通」として見られないのは確かだ。 恐い。ひどく恐い。常に日ごろから付き纏う恐怖心に追い立てられる。 だが、ふと、羞恥を感じる必要がない事を思い出した。 そうだ。 これは現実に起こっている事ではないのだから。 どういう訳で自分の見る夢の中で、ここまで恥ずかしい思いを、恐い思いをしなければならないのか。 それは解らないし、自分に自虐的な嗜好があるのかが心配で、釈然としない。 まあ、とにもかくにも、この青年に会うことも、こんなに綺麗なものを見る機会も、もう無いかもしれない。 夢はうつろいやすく、気まぐれなのだから。そして酷く一方的で、夢の世界の住人に気を遣う必要などない。 だから、この場所で思い通りに行かないのには、納得いかなかった。 睨むかの如く青年を一瞥すると、先程の彼の言を無視して、また一歩、歩を進める。 「!? ……おい、待っ…!」 の行動に驚いた青年が、咎めるように顔を歪めた。 それに構う事無く、光の流れへ近付く。 「…これは……?」 見たことのない、一つ一つの奇妙なそれ。 洪水の如し流れは、不思議な光を放つ数え切れないそれらによって構成されていた。 甲虫のようなもの、ミミズのようなもの、植物のようなもの、クラゲのようなもの… そのどれもが、見たことのある物に似ていて、そのどれもが、見たことの無い奇妙なモノ。 挙げた例えは、どれもあまり得意なものではなかったが、不思議とそれを気持ち悪いとは感じなかった。 むしろ、触ってみたい、と、もっと近くで見たい、と、強くそれらを感じたい、と、思った。 引き寄せられるように足を踏み入れると、青年はいよいよ立ち上がって、こちらに向って何事かを叫んでいる。 魅入られるように、その光の生物を感じる事以外に、五感は鈍くなっていた。 そもそも、どうしてこんなに曖昧な空間の中で、五感を鋭く保てようか。 ふわふわとした感覚がいっそう強くなる。ざぁ、と、河の半ばまで進むと、腰より下は、光で見えなくなった。 ああ、すごい。 気持ち悪いくらい、気持ちいい―――― ぞわぞわする。同時に足の爪の先からたちまちのうちに満たされていく。 金色の流れは、まるで自分の中に染み込んで通り抜けて行くようで。 「あんた、何をやってんだ!早く其処から出ろ!あちら側に引き込まれるぞ!」 意外にも、さっきよりも青年の声を近くに聞いたので顔を上げると、河から少し離れた所にいたはずの青年は 川岸ぎりぎりにまで近付いて、切羽詰ったように怒鳴っている。 はそこで初めて、その青年をはっきりと見た。 白い髪、片方しか見えない瞳は、碧色。明らかに、「普通」ではないその容姿。 一般人からは外れた風体であった。 物珍しく思って、しばし、その青年を見つめる。 別段、テレビで見るようなタレントのようにカッコイイとかそういった事はなかったが、恐らく「いい男」の 範疇ではあると思う。だが、それにしては、その青年には惹きつけられた。 色が、ある。 変な話、そんな風に思った。白い髪は、きれいに白くて、碧の虹彩が、鮮やかに生に彩りをのせている。 轟轟と、その間も淡く金色に光る河は流れ続ける。ここは、なんだか全てがとても綺麗。 「まさか……何ともないってのか…?」 (……何がだろ?) しばらくして、戸惑ったように青年が言った。意味をはかりかねて、首を傾げる。 どうして、こうも青年はこの光の河を、まるで禁忌だとでもするように言うのだろう。 こうして浸かっていても、何の害もないし、むしろ心地いい。 流れを体に感じると、色んなモノが洗い流されていくようだ。苦しみも、恐怖心も、意識さえ。 夢は得てして脈絡のないものだから、彼の言う事は、もしかすると気にする事はないのかもしれない。 そうこうしているうちに、どんどんと意識は流されて、ふわふわした感覚が強くなっていく。 (ああ…もう、時間なのかな……) 夢の中で意識が薄れていくのは、きっと、現実が「私」を手繰り寄せているから。 現実にある、私のものではない体を、唯一動かすことができるのは、ここに…夢の中に今いる「私」だけだから。 この不思議な、出来事の終わり。 そうして、目覚めて、私は生きる。 という名を持つ体を纏って、空虚に生きるのだ。 「どういう訳だか解らんが……オイ、いくら平気だっつってもな。流石にその状態で寝…」 河に入ってそのまま、うつらうつらし始めた自分を、青年はまさかと思いつつ心配したのだろう。 だが、そのまさかだった。 ばしゃん と、青年が最後まで言うのを待たずに、足がすくわれて、完全に流れに身を任せる。 「まじか…」 呆れきった顔に、吃驚と焦りを滲ませたという複雑な青年の顔を、金の奔流ごしに見た。 そんな顔をしつつも、川岸を小走りに自分を追ってくる。 多分無駄な事なのに、掴まれ、と、手を伸ばして助けようとしてくれる。 ああ、これが現実ならば、即効でこの男性に惚れていたことだろう、と思った。 つり橋で出会った男女は、恋に陥りやすい…ストックホルム症候群だっけ。 極限の状況下での生理的興奮は、異性に抱く恋愛感情のそれと大差ないらしく、恋だと思い込んでしまうというアレ。 今も、急流に流されている自分と、それを必死(?)で助けようとしてくれている青年。 条件的には揃っているが、生憎と、自主的に入水して、自主的に流されているのだから格好つかない。 加えて夢の中の誰とも知らない人に、恋をしてどうする。 「あの、どうぞおかまいなく……」 これは、夢なんで、どうぞ楽にして下さい。と、追いかけてきてくれる青年に、流されながら手をふった。 初めてこちら側から話しかけた。夢の中で、誰かに向って言葉をかけるなんて奇妙な感覚だ。 だが本当に、自分が作り出したただの願望像にしてはリアルに出来ている。 そんな呑気な言葉に、青年は思いっきり「はァ?」という言葉を顔に貼り付けて、 遠慮もなく盛大に訝し気な顔をした。 「えーと、さようなら。……その、また……会えたらいいですね」 取り敢えず、最後なのだから感想を言ってみる。見ようと思って見られる夢など無い。 またここに来れるという事も、青年に会えるという事も、これから先、全く保証はないのだから。 心残りのないよう、気持ちのいい別れ方をしよう、と努めた。 心は大分軽くなった。とても綺麗なモノも見れたし、やはり今思い出しても恥ずかしかったが、思いっきり泣けた。 そして何より、根拠はないが、自分を気に掛けてくれた「いい人」と、出会えたと思う。 夢にしては大満足だ。毎日こうなら、せめて心が楽なのに。 いつしかは覚醒へと向っていて、もう、その場の何もかもが視界から消し飛んでいく。 目を閉じて、全てを任せると、現実での目覚めを待った。 光の河は、何の異変もなく、そのまま流れていく。 まるで何事も無かったかのように、流れ続ける。 「…何だったんだ……ありゃあ」 結局あの妙な女が沈んで見えなくなり、途方もなくなってしまったので、走っていた足を止めた。 無理やりにでも、助け出すべきだったのだろうか。 目の前で人(?)が一人、どうにかなってしまったというのに、あのあまりにも面妖な態度に、 後悔も不甲斐なさも何も感じずに、ただただ呆れかえるしかなかった。 あの様子では自分がどういった状況下にいるのか、どうなってしまうのかを、理解していない可能性が大きい。 その証拠に、「また会えたらいい」などと、頓狂な事を言っていた。 いつものように、瞼を閉じた。 いつものように、光の河が見えた。 いつもはいない、見知らぬ人間がいた。 脈絡がない。いったい何だったというのだろう。 溜息を、ついた。 「会うもくそも、ないだろうよ……」 闇を貫く光の河の遥か彼方を、見つめながら、彼は呟いた。 |
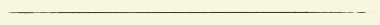
蟲師+トリップという無謀な挑戦
←back next→