
your name
(どうしよう……怒ってる?怒ってるよね……) もちろん謝った。 けれど、どんな風に謝罪を持ち掛けてみせても、ソーマはむっつりと口を閉ざして腕を組んだまま。 相変わらず顔の殆どがフードで隠れて、必要以上に接しにくさを醸し出している。 「ほ、ほんとうにすみません……あんまりにも喉が渇いていたもので、つい……」 同じような言い訳台詞を、何度も訴えかけているのだが、ことごとく気まずい独り言になっている。 手の中の空き缶?(どうにも見慣れない形状をしている)を持て余して、自己嫌悪に陥る。 (一口だけ分けて貰うつもりが……飲み干しちゃった……) 先程、ソーマが取り出して飲んでいるのを無意識に凝視してしまっていて。 至極鬱陶しそうに彼が差し出したものを、生存本能とでも言おうか。 何だか不思議な味だったけれど、干物になりそうだったところには甘露すぎて。 (うわあ、何やってるんだろう私……さっきから迷惑ばっかり掛け過ぎ) どんよりと落ち込んでいる所に、足音が近づいてきているのに気付いて、びくりと肩を揺らす。 思わずソーマの方を窺うけれど、少しだけ顔を持ち上げている以外、彼の様子に変化は無い。 やがて向こうから歩いてくる二つの人影が確認できた。 「……遅い」 低く不機嫌極まりない様子でソーマが呟いたが、大して気にした風もなく、相手は肩を竦める。 「こりゃまた、ご挨拶だな。残りの仕事をこなして此処まで迎えに来てやったってのに」 「依頼にあったターゲットは、これで全部ね。ソーマも、お疲れ様」 やはりこの荒涼とした世界にも他にも人がいた。更に安堵感が大きくなるのを、心の中に感じていた。 「いやァしかし、運のいいお嬢さんだ。こんな所までアラガミに出くわさずに逃げて来られたなんてな」 ふう、と煙草をふかしながら、此方に背をむけた男性が感心したように言う。 「本当に。……でも、助けたのはいいけれど、怪我の手当てもせずに放置するのは"保護"とは言わないわよソーマ?」 きゅ、と腹部の包帯を結び、丁寧に肌蹴ていた衣服を直してくれた女性は此方に微笑んだあと、 再び腕を組んで俯いている少年に向かって苦言を呈したが、本人は素知らぬ顔を僅かに逸らせて無視した。 この男女はおそらくソーマが先程通信していた相手だろう。携帯する武器からして彼らは仕事仲間のようだ。 「まったく……回復錠くらい、持ってなかったの?」 黒い髪を肩の部分で切りそろえた女性が、美貌を曇らせながら問うと、 「どーせコイツのこった。また無茶やって早々に使い切ってたんだろ」 同じく黒髪の端正な風貌の男性が軽口を叩く。図星だったのか、ソーマは苦い顔で舌を打った。 「……さ、これでいいわ。でも、応急処置だから、早く戻ってちゃんと診て貰わないとね」 ありがとうございます、と深々頭を下げると、「気にしないで」という言葉と共に極上の笑顔が返ってきた。 「ん、終わったか」 女性の言葉を聞いて、真摯にも手当ての最中は向こうを向いていた男性が此方を振り返る。 「無事で何より。だが、いくら気が動転していたとはいえ、外壁の外へ逃げ出すのは判断としては間違ってるな」 腰に手を当てて忠告するように言う男性の言葉が理解出来ず、首を傾げる。 「……外壁?」 鸚鵡返しに問うと、言葉が通じなかったのを少し意外そうに表情に浮かべながらも、続けてくれる。 「外部居住区を覆ってるアラガミ装甲の事だ。……ま、今日みたいに突破される事も多い代物だが、 外にいるよりはずっと安全だと思うがな」 男性はいい加減な調子ながらも、その実懇切丁寧に説明をしてくれている、とは思うのだが。 彼の口にする言葉のどれもこれも、まるで理解出来ない事ばかりだった。 「ええと……」 「……ん? お前さん、今日の襲撃で居住区から外に迷い込んだクチじゃないのか?」 襲撃って、何から?もしかしなくても、さっきの化け物みたいな生物の事だろうか。 そういうモノから守られた「居住区」という場所が存在していて、自分もそこから来たんじゃないかと問われているのか。 しかしながら、そんな場所にも記憶にも、覚えが無い。 「リンドウ。きっと彼女、まだ混乱しているのよ。……ごめんなさい、急に問質すみたいな真似をしてしまって」 落ち着いた声で、女性が優しく言葉を掛けてくれる。 諌められる形になってしまった"リンドウ"という男性は煙草を持っていない方の手でこめかみを掻いてみせた。 「私はサクヤ。こっちはリンドウで、あの子はソーマ。3人共、フェンリル極東支部所属の、神機使い<ゴッドイーター>よ」 サクヤは、一つ一つを組み立てるように、こちらの心をほぐすように言葉を紡ぐ。 「私達は、外部居住区を襲って逃走したアラガミを掃討する任務を受けて此処へ来たの。 それもさっき終わったから、もう大丈夫。……さ、私達と一緒に戻りましょう」 「……フェン、リル? ……ゴッドイーター?」 どんなに落ち着いて状況を説明されても、呑み込めなかった。どの単語も、聞いた事もなくて、非日常すぎて。 「アラガミ……って、さっき襲ってきた怪物の事ですか?」 「ええ、そうだけど……」 サクヤは困った様子でリンドウの方を窺ったが、彼も片眉を僅かに寄せる他、リアクションできないようだった。 その向こうで、ソーマが無表情に此方を窺っている。 「分らない……かしら。……それじゃあ、貴女の事を教えて貰える?」 気を取り直して、つとめて笑顔で訊ねてきてくれる。 「私の事……」 「貴女の名前は? どこから来たの?」 心は、落ち着いている。喉の渇きも癒せたし、傷の手当もしてもらった。もう焦る事も、混乱する事も無いはずなのに。 「はい、私は……、……」 言おう、と開きかけた口が、止まった。 当たり前に口から出て来るはずのものが、出てこない。思い出そうとしても、空を切る。 「わたしのなまえ……は?」 「おいおい、まさか……」 暫くしても答えられないままでいると、リンドウが煙草の煙を吐き出した。 「ココはドコ、私は誰……なんて、定番通りの展開じゃないだろうな」 そんなの、こっちの台詞だ、と戸惑う心の中で思った。 どうして自分がこんな状態なのか、自覚も実感も全く無い。けれど、名前も、具体的な素性も思い出せない。 自分が過ごしていただろう日常の情景が脳裏には思い出せるけど、まるで数日前に見たドラマのように断片的だった。 「ええと、ごめんなさい。思い出せなくて……」 「それじゃ、どこに住んでいたのかも?」 記憶が欠損している事を素直に認めると、サクヤの表情に気遣いの色が増した。 でも、まっさらに全て忘れているわけではないのも確かだ。 「はぁ……日本のどこか、ってくらいしか……」 「……えっ? "日本"?」 途端、目を丸くしたサクヤの様子に首を傾げる。 さっき街で見かけた看板や破れた広告片などには日本語が書かれていたし、彼らの話している言語も同じく。 何かおかしな事を言っただろうか、とリンドウの方にも視線を遣るが、飄々として動じる事のなさそうな表情は変わらず。 「ほう。最近の若者にしちゃあ、また随分古い言葉を使う」 「古い?……って……ここは日本じゃ、ないんですか?」 確かに、自分の記憶とは全く違った世界になってしまってはいるけれど。 恐る恐る投げかけた問いに対して、サクヤは首を横に振る。 「いいえ、合ってるわ。……でも」 「ここが――極東が、"日本"と呼ばれていたのは、昔の話だ」 さらっと、何でもない事のように言われた言葉に、耳を疑った。 「え……どういう……」 漏れ出た呻き声は、重なるように鳴り響いた通信機からの音に掻き消される。 ポケットから取り出した端末を一瞥したリンドウは、携帯用の灰皿に煙草を捩じ込んだ。 「おっと、そろそろ自己紹介タイムは終わりだな。名残惜しいが、帰投時刻が迫ってる」 「ねぇ、どうするの?身元が分らないんじゃ、彼女をどこに連れて行けばいいか……」 目の前で身の振り方についての話が上がっているのに、呆然としている事しか出来ない。 色んな情報が、同じく色んな部位が抜け落ちた自分の頭の中に入り込んできて、整理がつかずに更に散らかっていく。 私は多分、日本の、普通の高校生だったはずで。でもそれ以外、名前も、家族も、住んでいた場所も思い出せない。 かつて日本だったここは極東で、アラガミという怪物がいて、街がめちゃくちゃになってて、武器を持った人達がいて。 でも、何でそんな所に自分はいるんだろう。 考え込む此方を他所に、リンドウは「残念だが」と言いながら、腰に手を置いて諦めたように溜息をつく。 「俺達はアラガミをブッ倒して喰らう事くらいしか能が無いからな。お嬢さんの事は、医者に任せた方がよさそうだ」 「もう、投げ遣りなんだから……。でも、さっきも言った通り、病院でちゃんとした手当てを受けた方がいいわ。 ともかく私達と一緒に戻りましょう。歩ける?」 訳が分らないままだけれど、もしかしたら本当に頭関係で医者には診て貰った方がいいのかもしれない。 あまりにも抜け落ちすぎている。 「あ、はい、お世話お掛けしてすみませ……ぐあ!」 同行の申し出は非常に有り難い、と、喜んでついて行こうと立ち上がったが、両足にはしった痛みに悶絶する。 ここに至るまでに負った傷だとか捻挫だとかが、予想以上に深手だったのに全く気が付かなかった。 「やだ、大丈夫?……そういえば貴女、靴も履いてないじゃない。怪我も酷いし、歩くのは無理そうね」 慌てて身体を支えてくれたサクヤに対して謝りながらも、何とか歩けないかと足の裏を砂地につける。 これ以上面倒を掛けるのも嫌だったし、何も出来ない分、出来るだけ彼らの邪魔にはなりたくない。 焼けるような、或いは刺すような痛みが下から突き上げてくるけれど、立ち上がる所までは何とか出来た。 「だ……だ、だ、大丈夫です……折れてる、わけじゃないしっ」 がちがちと噛み合わない歯の奥から言葉を搾り出し、悲鳴を抑えて必死で平気な風を装うけれど、 サクヤとリンドウは呆れたように各々肩を竦める。ソーマは向こうで、既に帰途につきかけているのが見えた。 「……ふむ」 やれやれ、と腰に当てていた両手を離し、リンドウは片方で大きな武器を肩に担ぐ。 「おい、ソーマ。このお嬢さんを負ぶってやれ」 そうして、去り行く少年に向かって投げかけられた言葉に度肝をぬかされた。衝撃で、頭の中が一瞬真っ白になった。 「――い!? いやっ、それは……」 なんて事を軽い調子で言ってくれるのだろうか、このお方は。 出会って間もない自分が言うのも変だが、リンドウにしろサクヤにしろ、ソーマのあのキャラに対して遠慮が無さ過ぎる。 おそらく付き合いが長いが故の気安さなのだろうが、そこに自分もくっつけて遣り取りするのは勘弁して欲しい。 恐々と、少し離れた場所で立ち止まったソーマの様子を窺う。フードを被った首が、少しだけ後方を顧みた。 「断る」 不愉快な様子を含ませてきっぱりとした答えが返ってくる。予想通り過ぎる応えに片頬が引き攣った。 何だか気を遣ってもらった筈だったのに、結果としては逆に傷ついたような気がする。 「やれやれ。上官の命令に逆らうたあ、いい度胸だな、ソーマ」 リンドウは眇めた目をソーマに向けた後、ひょい、と足元に置いてあった先程のジュースの缶を拾う。 あ、そういえば手当てして貰う時、ひとまず手放したんだった。 「……ったく、任務への菓子の持込も併せて、軍規違反として報告した方がいいか?」 言いながら、空の缶を顔の横で振るが。 「……好きにしろ」 脅しめいた物言いに対しても、気にした風無くソーマは此方から顔を背けた。 そうして彼が歩みを再開させたのを、サクヤも呆れた表情で見送っている。 上官命令といっても、彼の軍規違反とやらが自分のせいみたいでしのびない。 歩くのを怠っている人間を、何の筋合いでか背負えと言われたのに対して断っただけなのだし。 ジュースに関しては、持ち込んだのはソーマだとはいえ、中身は殆ど自分が飲んでしまったし。 しかも、空になったのに捨てないで目に付く形で持っていたから、見つかってしまっているわけだ。 「あ、あの……」 「ん?」 意を決して、声を掛けてみる。片手で器用に玩ばれているジュース缶を指差した。 「それ、私が持ってたもの、です……」 大した事がないとはいえ、嘘は苦手だ。 恩着せがましくなりかねないので、ソーマには聞こえないよう小さな声で言うと、結果何とも弱々しい物言いになった。 リンドウは「ほう」と、納得したような、何かを勘ぐるような返事をして、此方を窺う。 軽口を叩いたり、いい加減そうな態度や仕草をとるような印象はあったが、その実、彼の眼差しはどこか深く鋭い。 見透かされているような感覚に居心地の悪さを感じつつも、主張は引っ込めなかった。 「なるほどな。真っ先に部下を疑うなんて、俺は隊長失格だ」 嘘か本気か、肩を落として反省の意を示したリンドウから、空き缶を受け取る。 一抹の気まずさを感じながら、それを両手で握った。 「その空き缶は大事に持っとくべきだな。身元の判明に、大いに貢献できる代物だろう」 「……え、何で、ですか」 たかがジュース。リンドウの言うような、そんな重要な物とは思えなくて、背中に汗が滲んだ。 ふふっ、と笑い声が聞こえたのでそちらの方を向くと、サクヤが微笑みながら小首を傾げている。 「嗜好品の配給は数も決められているし、一般人には手に入れ難い物が殆どだものね」 ジュースすら、配給制になっているのか、と唖然とした。 この街の衰退具合からして、元から自給率の高くない日本のこと、食糧事情は芳しくないだろう事は予測出来るけど。 となれば、配給対象者のリストを洗えば、身元は絞られてくるはず、という事をリンドウは示唆しているのだろう。 ただし、こちらの嘘も、どうやら二人の態度からして既にバレているように思う。 また大して役にも立てず下らない事をしてしまったなぁ、と落ち込んでいたところ、ふいに声が降ってきた。 「……おい、まだか」 もう随分先に行ってしまっていると思っていたソーマが、立っていた。 相変わらず乏しい表情の浅黒い顔には、不機嫌そうな色がのっている。 「一人がグズなせいで、タイムオーバーで報酬が減らされちゃ堪んねえ」 リンドウとサクヤの間をすり抜け、目の前に立った彼からは独特の威圧感を感じる。 「……う…」 睨むような視線で射られて思わず後ずさろうとするが、ぐいと腕が引っ張られてあっという真に背負われる形になる。 こちらの体重など全く意に介さずというほど軽々とした動作に、抵抗らしい抵抗をする暇もなかった。 身の丈程もある重厚な武器を振るっていただけあって、力はあるのだろうが。 「あ、あの……」 申し訳ないやら畏れ多いやら、何か言おうと口をもごもごさせるが、「うるさい」と間近から釘を打たれた。 「迷惑だ。お前が此処にいるのも、変な勘違いをされるのも。詫びるつもりなら黙ってろ」 冷徹な声。 だけれど、少し振り返って見えた彼の仲間二人は、結局戻ってきた少年に苦笑していた。 これ以上何か気に障る事をして放り投げられでもしたら堪らないので、「ごめんなさい」は心に仕舞って口を噤む。 年の近い異性に負ぶって貰うのは、身の置き場に困るほど恥ずかしい。 「………」 でも、やっぱり何故だか、安心する。 リンドウとサクヤが、今晩の食事メニューについて話す落ち着いた声が、背中に聞こえる。 そこに加わる事もなく、ソーマは無言で彼らから少し離れた先をもくもくと歩いていた。 傾きかけた落日の光と、触れる背中が暖かい。ごく近い所に感じる息遣いや、足音や、鼓動が、心地いい。 ちょっと前までの絶望や恐怖や不安が大きかった分、それらは自分を優しく包んでいく。 まだ今しばらく思い出せない中には、こうして負われて歩いた記憶もあるのだろうか。 どうして、何も分らないのだろう。 どうやって、こんな場所に来てしまったんだろう。 どこに、自分は帰るべきなのだろう。 言われた通りに黙って一人で考え込んでいると、答えの見えない迷路の中、心地よい振動に段々と意識が薄れてくる。 ソーマの背中にいると緊張しっぱなしで、眠気どころじゃない筈なのに。否、その分疲れるのが早いからだろうか。 「そういえば、貴女、年は? ……あ、覚えてないかしら」 暫くして、どうやら此方に対して放たれたらしい声に、首だけで振り返った。 「……えっと、高校で、受験……勉強してたと思うから、多分……」 少し後ろを歩いているサクヤからの問いに、重たい瞼と格闘しながら答える。 「じゃあ、18?ソーマと同い年ね」 前方から小さく舌打ちが聞こえたのは、勝手に話題のネタにされている事が気に入らないからだろうか。 大人びた印象もあったけれど、同じ年と聞くと、彼に対して少し親近感が湧く。迷惑だろうが。 「でも、こんな世の中で受験なんて。もしかして、どこかの令嬢だとか、研究員候補の学生さん……だったりして?」 受験勉強をしてるというだけで、令嬢や研究員志望に繋がる程、学生が希少な時勢なのだろうか。 「いえ……私なんか、普通で……頭も……そんな、に……」 何とか答えられたのは、そこまでだった。 あとは頭を働かせる余力なんて無くて、睡魔があっというまに意識を侵食していく。 重くなって支える事のできなくなった頭が、柔らかなフードを被った肩口に沈み込んだ。 「……あら、寝ちゃった?」 サクヤのそんな声が聞こえた気がするけれど、どんどんと、暗い眠りの淵に引き込まれる。 「そりゃ、こんな災難な一日とあっちゃ、疲れて当然だろう。……おいソーマ、少しは気を遣って運んでやれよ」 「……知ったことか」 ずり落ちそうになった背中の荷物を、ソーマは乱暴に背負いなおす。 棘を含んだ低音での彼の返事に、後ろを歩く二人は顔を見合わせて肩を竦めた。 「見かけによらず猛者らしい。よくもあんな場所で眠れるもんだ」 リンドウの軽口にサクヤがクスリと笑みを漏らした。 「……ん………さん?…………さん?」 聞いた事のない声と呼び名だったけれど、直ぐ傍から降ってきたのもあって、思わずはっと目を覚ます。 白い壁が冷たくて薄暗い印象を与える廊下を背景に、看護士らしき女性が此方を覗き込んでいた。 「……え……あ?」 またも何がどうなっているのか解らず、無理やりこじ開けた瞼を擦りながら起き上がる。 「さん……で、合ってるかしら?もう他の方は診察を終えられたので、残ってるのは貴女だけなんだけど」 受付名簿と問診表を見ながら、片方の眉を顰めて看護士は言う。 ゆるゆると自分の状況を確認してみるが、やっぱり限られた記憶しか無い上、足も腹も怪我をしていて痛い。 どうやら此処は病院で、言われていたように、ちゃんと診て貰うよう連れて来られたらしい。 窓の外に見える空は暗く、いつのまにか彼らの姿はすでに無かった。 (まあ、そこまで付き合う義理もないだろうし……) どこやらの所属のナントカ使い、と言っていた彼らは、職務を果たしたまでだ。 むしろあんな場所から助け出してくれて、病院に送り届けるまでしてくれた、彼らの親切に感謝の想いが湧いてくる。 ただ、まっさらで不安な所に差し伸べられた手に、必要以上に懐いてしまった分の寂しさは残る。 「あの、聞こえてます?さん」 様子を訝るような看護士の声に気が付いて、慌てて「すみません」と頭を下げた。 しかしその名前に覚えは無い。というか本当の名前も覚えてないのだけど。 「えーと、私、その……何も覚えてなくて」 「覚えてない?……じゃあ、この問診表に心当たりは有ります?」 バインダーに挟まった一番上の紙を外して寄越されたものを、まじまじと見る。しかし、それは殆ど白紙に近かった。 たくさんある質問項目の中で、埋められているのはたった三つ。 随分と投げやりな字で、年齢の項目に「18」、備考欄に「頭を打った」と書かれている。 「有るような……無いような……」 信憑性があるのは年齢だけで、備考欄はどことなく失礼な気もする。 「あんまりと言えばあんまりな内容なんで、ふざけているのかと思ったんですけど……名前は合ってます?」 埋められた項目のあと一つ。 名前欄の左上に一点、考え込んでついたようなインクのシミのあと、「」と記されていた。 どうしてか、あのフードを目深に被った、冷たい印象の少年の姿が思い浮かんだ。 埋められてない沢山の項目や、ぞんざいな回答は、その可能性を高める材料になる。 (適当に名前……つけてくれた、のかな?) そうかもしれない、と思うと、いまだ燻ぶる不安が和らいで、唇の端が上がった。 「……はい、多分。私は、です」 つけられたばかりの名前はまだ馴染まなくて、少しだけ気恥ずかしかった。 |
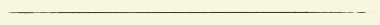
名付け親はソーマでした
←back next→