
narrow road
薬剤のにおいに僅かに頭痛を覚えながら、カルテに奔るペン先を目で追う。 「応急処置が幸いしたね。出血のわりに傷は深く無いから、すぐ治るだろう。問題は……」 文字の最後にピリオドを打ち、先程撮った頭部のレントゲン写真を眺めながら、初老の医師は首を捻った。 「頭部に目立った外傷も無し。これといって異常も無いみたいだがねえ。心因性ショックか、あるいは……」 顎においていた手で髭の生えた輪郭を一撫でして、視線だけ此方へ寄越す。 「……いや。取り合えず、いくつか確認をしよう。君の名前は""で、年は18」 問診表をチラリと見ながら内容をそのまま読み上げて、此方に確認する。 背もたれの無い丸椅子の上で姿勢を正しては頷いた。 「はい。……本当の名前じゃなくて、つけて貰ったものですけど」 「なるほど記憶が無いなら仕方ないだろうね。では、年齢の方は?」 「おぼろげですけど、大学受験を控えていたような記憶があって……」 カルテを引っ掻くペン先のスピードは変わらない。 けれど、医者の眉間には訝しむような皺が少しだけ寄った。 「……記憶を失くした後の詳しい状況は?」 覚えている記憶には触れる事無く、問いが続けられる。 何かおかしな事を自分が言ってやしないか不安だが、どうも既に記憶喪失だと自称している時点で手遅れなようだ。 「気が付いたら、荒廃した街を歩いていたんです。どうやってあんな場所に行ったのかも、何があったのかも分らなくて」 「贖罪の街……か。ここから人の足では随分遠いが……」 あの場所には名前があるのだろうか。医師の口にした名の街は、平和な日本とは思えない程荒れ果てていた。 「……あそこは、どうしてあんな風になってるんですか? 変な化け物までいて……」 おそるおそる訊ねた言葉に、医師は些かの驚きと、酷く怪訝そうな様子を混ぜた表情をこちらに向ける。 サクヤ達の時と同じだ。どこか自分の感覚や認識は、周りからずれているように感じる。 何度かそれを突きつけられても、未だに慣れる事は出来ないし、当然相手に受け入れては貰えない。 「どういう意味だい?今や、どこもかしこも"あんな風"だし、"変な化け物"がウヨウヨいるが」 「ウヨウヨ……って…… いったい、どうなって……」 ショックを受けて呆然と問い返した先で、お話にならない、とでも言いたげに初老の男性は溜息をついた。 「ターミナルへのアクセス権を偽装して、過去の動画や画像のログを漁るのが若者の間で流行っているらしいね」 「……え?」 言いたい事が分らない、と困惑を顔に示した。 「そう、"変な化け物"にいつ喰い殺されるか知れない。そんな世の中だ。目を背けたくもなる気持ちも解る」 「は、はあ……」 相変わらず言葉の真意は解らないが、何だか諌められているような心地になる。 「これまでに精神科にかかった事は?」 構わず、医師は眉を顰めたまま、此方の事を無視して問い掛けを続けた。 段々と、自分がどういう風に扱われてきているのか解ってきた気がした。それと共に目の前の大人への不快感が増す。 「だから、それは覚えてないですけど………私、正常です」 此方の言う事を、虚言や精神疾患が原因のものとしてしか聞いてくれていないんだろう。 「記憶が無い状態を正常と言うかね?……それに、それは君が判断する事じゃない」 「でも、本当です。以前の記憶が殆ど無いのも、私の知っている日本が、こんなじゃないのも。 私が判断しちゃいけないんなら、ちゃんと……」 「ちゃんとした判断を下すには精密検査をする必要があるが、その費用を、どうするんだい」 問われた事は至極当たり前で、とても現実的な問題だった。そうだ、今回の診察料の事だって考えていなかった。 医師はカルテとは別の書類に目を通しながら、また溜息をつく。 「今朝の襲撃による行方不明者を含めたリストにも、該当しそうな人物は無し。 その他、さっき採らせて貰った血液と指紋を、フェンリルのデータベースで照合してみたがヒットは無かった」 何を言われているのかいまいち解らないけれど、自分には戸籍や身分証明出来るものが無い、という意味に違いない。 「そうなると、君の記憶とやらも怪しいものになる。フェンリルの庇護下にない人間が高校に在籍しているなど……」 「……そんな」 金銭的な問題を指摘するだけでなく、回りくどいが、こちらの証言が嘘偽りであるという答えに持っていかれてしまう。 或いは、名前はともかく今有る記憶が全部、思い込みの産物である可能性がある、と。 そんな事絶対にない、と反論出来る根拠も無ければ、自信も無い。 膝の上に結んだ拳を、少しだけ強く握り込んだ。 ところで、先ほどから耳にする「フェンリル」というのは、余程影響の大きいものらしいように聞える。 「その、フェンリル……って、何なんですか?警察か、政府か何かなんですか?」 訊ねると、「いいや」と医師は首を横に振った後、ややあって「そうとも言えるかもしれん」と頷いたりもしてみせた。 「生物化学企業。アラガミの脅威に軍も政府も無力化した後、かの機関が唯一の対抗手段の開発に成功した。 その使い手達を統率指揮し、各地に防壁に囲まれた都市"ハイブ"を造り上げたのが彼らだ」 化物を切り裂いた、ソーマ達が持っていた大きな剣。あれが人類に与えられた武器なのだろうか。 そういえば、サクヤからも同じような言葉を聞いた気がする。フェンリル極東支部……神機使い――ゴッドイーター。 彼らのように武器を持たなければ、あのアラガミとかいう化け物の餌食になる。 その唯一の対抗策に人々は縋るしかなく、「フェンリル」は必然と世界の頂点に立つ事になったと。 そうして、そんなギリギリのディストピアで、人間は辛うじて生きている。 自称記憶喪失の自分にも解りやすいよう、医師は説明をしてくれた。 「……でも、それじゃあ……私の覚えてる事は……」 私は普通の高校生で、日本は平和で、日常は退屈で冷やかで変わり映えもなく。 「きっと戯れに見た過去のログが記憶に残っているんだろう」 それが最初から、彼の出していた結論であり、本音だったののろう。 成人もしていないような人間が、「昔の日本」を知っているというのだから。 「そんな幻想は、君の生まれる前から何処にも有りはしない。世界はアラガミという天敵に侵食され、 生き残った人間は、こうして身を寄せ合って生きていくしかないのが現状だ」 「…………そん、な……」 過去のログって何? 幻想なんかじゃない。そこで生活していた事を身体が覚えている。 "アラガミ"なんて化け物がいない世界を、豊かでどこか虚しい日々を私は知っているのに。 それさえも、自分が作り出したニセモノなんだろうか? 日本ばかりじゃなく、世界まで荒れ果てて。 平和な場所も、安全が保障された社会も、どこにも無いんだと頭で言い聞かせても、実感がまるで湧かない。 理解なんてしたくなかったけれど、悪夢のようなこの状況は、覚める事なく続いている。 医師は厳しい眼差しで、茫然自失している此方を射抜き、肩を掴んで「しっかりなさい」と叱咤してくれる。 「ここは、"日本"じゃない」 まともに取り合ってくれない人なんだと蔑視しかけていたが、そうじゃなかった。 今此処で、少なくともまともじゃ無かったのは、自分の方らしい。 未だ信じられないし、納得なんて出来ない。自分の記憶がただの虚像だなんて、そんな筈は。 「わかるかね?その名が使われなくなって久しく、今は2071年。ここは"極東第8ハイブ"」 SF映画やアニメは出て来る言葉や設定が難しくって、あんまり得意じゃないっていうのに。 2071年?極東第8ハイブ?あまりにも馴染まない単語が呑み込めなくて、医師に対して何も反応が返せなかった。 時計の針は、午後10時を回っていた。 「……ふう」 照明スイッチを押してもその部屋は薄暗く、妙な圧迫感を覚えて、心身共の疲労に息をつく。 怪我もあるし、身元もまだ明らかになっていないという事で、今晩は病室を使うよう案内をされた。 明日には、この病院の管理運営も行っているフェンリル極東支部へ、個人情報や検査結果が提出されると聞いている。 今回の診療代も入院費も、家無し一文無しの今の自分にはどうする事も出来ないので、言われた事に対して頷いた。 頷いたのに、「本当にいいんだね」と、何故か念を押されたのが気になった。 フェンリルのデータベースに登録すれば配給も受けられ、ある程度の権利や保障も発生する、と説明されれば、 断る理由などあるはずもないのに。 硬い医療用のベッドの淵に腰掛けてうな垂れる。 「……2071年って……そんなわけないじゃない……」 耳が痛くなるほどの静けさに耐えられなくて、ぽつりとそう漏らした。 「……年賀状書いてたもん。今年もよろしくって、友達に……」 受験頑張ろうね、と、顔も名前も今は覚えていない友人へ、送った記憶がある。 面倒くさく感じるまで書きまくった数字に、50以上も足した年の世にいるなんて。 ぼんやりと、窓の外の夜景を眺める。 穏やかな夜空の下、文明の明かりが輝いている。まるで都内のホテルにいるような光景に見える。 こうして見る限りは、医師の話は全部嘘のように思えたが。 「……?」 ふと、違和感を感じた。 それを確かめようと、窓に近寄り、ガラスにひたと指をつける。 「……これ、本物……じゃ、ない」 驚く程良く出来たヴァーチャル映像が、さも窓の外に平和な世界が広がっているかのごとく映し出されているのだった。 さすが50年以上未来の世界の技術、と、脱力に似た感動を覚える。 確か、居住区や施設の殆どが地下にあるのだったか。此処もそうなのだろう。 感じた圧迫感や息苦しさの原因が解った気がする。 「過去のログ……か」 こういう風に、さも本物みたいな昔の映像を見た記憶に過ぎないと、言われたけれど。 ――本当に、そうなの? きっと違うと、自分は思っている。穏やかな陽光の温度や、季節の風のにおいを覚えている。 何気ないものでしかないけれど、それらは憶測や妄想で補完できるものでもない。 それらの頼りない記憶は、あまりにも「ここ」の空気とは違っている。 今はそれを証明する情報が不足していても、どうにかして取り戻していけるかもしれない。 精密検査を受けられれば。そして、相応の治療を受けられれば。 それにはお金が要るし、働くには、この都市を統括するフェンリルを介さなければならない。 「とにかく、身の置き場所をしっかりしなきゃ……まずは、自分の事をハッキリさせて」 それから……そうしたら―― 先の事に対しての思考を中断させるように、頭を振る。 今はまだ、深く考えてはいけない気がする。深く考えたら、恐い事や、絶望的な事が、心の中に押し寄せてきそうで。 今日と、明日と、明後日と……できればその先可能な限り、生き永らえる事だけを考えていかなくては。 冷たい指先を、夜景を映し出している画面から離す。 不安げな顔が、規則的に移ろう夜の街の上におぼろげに映っていた。 「………お礼……言えなかった」 ベッドに戻って目を閉じると、親切にしてくれた人達と、冷たく鋭い少年の姿が脳裏に浮かぶ。 優しい笑顔、頼り甲斐のある眼差し、誰かの肩口の心地いい温度。 この果てしなく先行きの暗い世界において、それらは過剰な程に自分の心に優しく残っている。 彼らを思い出すと不安は少し和らいで、眠気に任せて意識を手放す事がやっと出来た。 「受け入れが出来ないって……どうしてですか……!?」 高い檻のような壁に囲われた、家屋や施設が乱雑に建ち並ぶ街、極東第8ハイブ。 その中心部、現在の人間が持つに可能な限りの技術を駆使して建設されたフェンリル極東支部。 殆どの区画は民間人の立ち入りを禁止しているが、一階エントランスのみ、住民窓口として開かれている。 「居住区画は流入してきている方々で既に一杯で、避難民の受け入れは、現在出来ない状態にあるんです」 病院から放り出される際に言われたとおり此処まで来たが、窓口で聞かされた事実に、は愕然とする。 「そんな……でも、他に行く所なんて……」 胸から下がすうっと冷えていくような心地に、僅かに身震いした。 応対にあたった事務員の女性は、その台詞を言い慣れた様子で、顔には同情の色がのっている。 しかしそこで「ハイそうですか」と退散できるものでもない。 「あ、あの私、本当に何にも無くて、今朝だって病室のベッドが足りないからって、追い出されてしまって……」 何とか自分の切迫した状況を伝えられないかと食い下がってみるが、相手の困惑の相が深まるばかりだった。 断られた後には本当に何も無いのだ。手荷物も、お金も、行く宛ても。これからどうすればいいのかだって。 諦めきれずに言葉を探していると、エントランスの一角に設置されたスクリーンのような大きさのテレビから、 緊急のニュースを伝えるアナウンスが鳴り響いた。 フロアにいた人々は、各々一旦動きを止めて、大きなモニターに映し出されている映像に見入る。 こんな時にテレビなんて、と動作が遅れたが、毎日が緊急事態らしいこの世界では何より情報が重要らしい。 しぶしぶ画面を振り返ると、緊迫した面持ちの美人キャスターが此方へ強い眼差しを向けていた。 『……今日未明、西地区の外周防壁がアラガミにより一部破壊され、近隣の住民18人が死傷する事件が発生しました なお、西側外周防壁は先月の襲撃で修復作業中にあり……』 淡々とした口調で告げられるニュースに合わせて、蹂躙された家屋や現場を走り回る作業員が映し出される。 怪我をしてぐったりとした人や、無事だったものの、この世を悲観するかのように瓦礫の傍にしゃがみ込む人や。 「………」 どうりで、朝日も昇らぬうちから病院内が騒がしくなったわけだ。 昼夜問わず頻繁に襲ってくる異形のものたち。 確か昨日もソーマ達は別居住区におけるアラガミ襲撃からの追撃に来たのではなかったか。 住む場所もそうだが、日々医療の現場も人員も設備も不足している。 ちらりとフロアにいる他の人々の様子を窺うが、驚きもせず、ただその顔には疲労感と悲愴感が漂っている。 『また、同地区の広場では住民と難民によるフェンリルに対する抗議デモが連日行われ…』 なりふり構わず、即席の看板を掲げて、力の限り叫ぶ人々。 "私たちにも住む場所を"、"雇用の安定を"、"もっと配給物を"、"安全の強化を" それは、遠い外国の事じゃない。 今まさに、この建物のすぐ外で行われている事なのだ。 映画みたいなこの深刻な状況を、皆が受け止めている。あるいは引き摺りながら歩いている。 「すでに、第8ハイブにおける収容可能人数は超過した状態で……外にも受け入れ待ちの人が溢れているんです」 ニュースの内容に被せるようにして、苦い顔の事務員が低い声で言う。 (……私だけが特別困ってるってわけじゃ……ないんだ) 皆が今生の事に必死になっている。 こんな状況下で自分だけ助けてくれと訴えても、それが通る筈がない。 受付のカウンターに乗り出すように置いていた腕を、ゆるゆると退かせる。 どうにもならないのは痛いほど解ったがしかし、本当にこの後自分はどうすれば。 「……あのう、もし、データ登録をして、フェンリル管理下に入る事にご同意頂ければ、 配給や補助を受けられますし、期限つきで宿泊施設がご利用頂けますが……」 病院でも同じような話を聞いていた。 俯き加減の頭を上げて、今一度カウンターの向こうを窺う。 「………」 管理される事に同意を示すだけで待遇が変わるというのも怪しい話だ。 それは誰も頼る者のいない世界においては、先の不明瞭な、いまいち身の置き場の定まらない提案だった。 けれど、例え数日間だけでも、身の安全が確保出来るならば願ってもない。 糸のように細い道でも、歩く方向が示唆されているのなら其処を行くしかない。 「同意します」と、答えた。 「それでは、此方の内容によく目を通して、問題が無ければサインを」 細かい文字がズラッと並んだ書類の束を渡され、唯でさえ弱っている精神が揺らぐような感覚を覚える。 基本的な規則、義務が事細かに書かれているのだろうが、全てを飲み込む気力など無かった。 殆どを読み飛ばしながら、文章の最後を目指す。 「……えっと、この"適合候補者とみなされた場合の適合検査を受ける義務"っていうのは、一体……?」 「それは、偏食因子に対して抵抗が無く、神機に適合性があるとみなされた場合、検査しなければならない義務です」 説明されても、いまいちよく解らない。 「……うーん、と……健康診断みたいなもの……ですか?」 「適合検査の前に予備検査だってありますし、心配は要りませんよ」 事務員の言葉を耳に流し込みながら、紙面右下の署名欄に、仮の名前を書き込む。 捺印が必要な所には、同じように全て名前を書き込んだ。 「はい……様、ですね。ああ、既に病院から検査や診断書のデータは届いていますね。登録は完了です」 キーボードを叩いていた手を止めた事務員は、本来の営業スマイルに戻って頷く。 「では、配給品と補助金の引き渡し、仮部屋の手配をさせて頂きますので、フロアにてしばらくお待ち下さい」 ソファに腰をおろしてひと息をつく。そこで喉が渇いているのを自覚した。 所在なく周囲を見回してみて、ロビーの隅に自動販売機らしきものを見つけると、物欲しい気持ちになる。 けれど、今の自分は一文無しだ。 日本が無い今、馴染みある通貨が使えるのかは知れないが、持っていたとしてもジュースなんかには使っていられない。 いくらか世界の状況が解ってくると、ソーマの飲んでいた缶ジュースがどれだけ貴重なものだったのか、理解出来た。 (やっぱり、悪い事したんだな……いつか買って返せたらいいけど) 溜息を吐いて考えてみるも、武器一つで化け物相手に身を立てている彼らの域に届く事など、到底出来ないだろう。 それよりも、ここの地理も仕組みもいまいち理解出来てない分際では、彼らに再会する事すら難しい。 (そういえば、フェンリル所属って言ってたような……ここも、フェンリルってやつの一角なんだよね) 手掛かりを探すわけでもなかったが、何とはなしに彷徨わせた視線が、ひと組の男女を捉える。 「もう……ふざけてないで、ちゃんと報告をして下さい」 「ふざけてなんてないって!真面目も真面目。本気の話なんだよ、な?」 入口に近い住民窓口より、奥まった所、フロアの中央にあるカウンター。 一般人を牽制するかのごとく扉が邪魔をしてよく見えないが、隙間から半円形のカウンターに取りつく青年が見える。 「だからさ、ヒバリちゃん。その本気を示すためにも、今晩二人で食事でも……」 どうやら受付の若い女性事務員をナンパしにかかっているらしいが。 (あの赤いの……真っ赤な、腕輪……確か――) 青年の手首をがっちりと覆う、アクセサリーにしては異質な色彩と形状の物。 乾涸びた砂塵の向こうの光景が、脳裏に蘇る。 絶叫と涙を切り裂いて現れた、大きな武器を振う手。 あれは、ぶっきらぼうにジュースの缶を差し出してくれた手に嵌っていたものと同じ。 (リンドウさんや、サクヤさんも嵌めてたよね……でも、こっちの待合室や、受付の人とかは着けてない) 手枷にも見える赤い大きな腕輪は、何かを識別するための物なのだろうか。 例えば、サクヤが口にしていた"ゴッドイーター"と呼ばれる存在。 少なくとも、あの素気無くあしらわれている青年は、何かしらソーマ達と同じ要素を持ち合わせているという事だろう。 「さん、お待たせしました。………さん?」 「あっ……、すみません」 ぼんやりとした思考を突つかれて振り向くと、カウンターの向こうから先程と変わらぬ笑顔が此方を見ている。 どうやら手続きが済んだらしい。慌ててソファから腰を上げた。 「場所はE26エリア。これが部屋の鍵です。それと、病院からの請求額を差引いた分になりますが、補助金はこちらに」 「はい」と言って受け取った封筒の中には、やはり見た事のない紙幣や貨幣が入っている。 「配給品は後で部屋に送りますね。それと、慌ただしくて申し訳ないんですが、仮部屋の使用権は一月となっています。 フェンリルとしては、あくまで自立支援という形になりますので、求人掲示板をなるべくご確認下さい」 説明を続けながら、目で指し示された方を見てみると、カウンターの横にボードがある。 「色々と、ありがとう御座いました」 アルバイトなんてしてた記憶もないなぁ、という不安を抱えながらも、事務員の女性に頭を下げ、窓口を後にする。 さっそく、アドバイスの通りに求人掲示板とやらを覗いてみるが、たなびいているメモは数枚しかない。 「外壁修復現場作業員」「物資運搬ドライバー」「新薬実験」 目に入った内容に、思わず眉を顰める。 まだ若輩の、しかも女の身ではいささかハードルが高いように思われる。 どれも身を立てる途中で、身を滅ぼしそうな職種ばかりだ。 (これは……求人情報は更新されるだろうけど、慎重に決めた方が良さそうだなぁ) ちょうどテレビのモニターにも、住民達が雇用機会改善の看板を掲げて行進しているのが映し出されていた。 今にあそこに自分も加わる事になるのだろうか。 不安を押し隠すように、貰ったばかりの鍵を力を込めて掌の中に握りしめた。 辛うじて繋がった、細い細い往く道。 願わくばそれが途絶える事のありませんように。 |
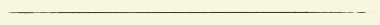
まだ迷走中
←back next→