
world end
厚く堆積した干からびた砂を踏む音が、響く。 埃や塵を多量に含んだ風が、頼りない布地からはみ出た皮膚を、痛みを伴うほどに撫で付けていく。 ざく、ざく、という足音だけが他人事のように耳に響いていた。 しかし、それが自分の発している音だと気が付いた時、濁っていた意識は現状に向けて大きく開く。 「………え……?」 酷く喉が渇いていた。 それが自分のものだったのかも解らないほど、声が掠れていた。 さらに、解らないのはそれだけじゃない。 たった今目が覚めたかのように、周りの景色が眩しく視界に飛び込んでくる。 「……なに、これ……?」 これ、というか、ここ、というか。 何かを育むつもりのまるでないような、容赦ない太陽の照りつけの下。 覚えのある景色からは程遠い、荒廃の限りを尽くした街が、広がっていた。 天を衝く程のビルが立ち並び、幾重にも高架の交差する様は人の築いた文明の栄華を物語っていただろう。 しかし、それらは無残にも食い荒らされ、抉られ、捨て置かれていた。 あるものは瓦礫の山となり、あるものはかつてのおもむきを残さずに風化に任せて佇んでいる。 ましてそこに人の気配など微塵もなく、それどころか衰退を促す如く風の音以外は、何の息遣いも聞こえない。 コンクリートで舗装されていたのかもしれない道路はあちこちが隆起して、積もった粉塵で砂漠のようになっている。 そして、その上に自分が立っている理由も、経緯も、全く思い出せない事に愕然とした。 (どうして……? 何で……? どういうこと?どうなってるの?何で私……) 疑問が深まっていくのにつれて、どくんどくんと、心臓の脈打つ音が大きくなっていく。 何もかも解らなくて、直前までの記憶すら皆目思い出せないのも不安な心に更に拍車をかける。 振り返って自分の来た道筋を探すけれど、少し向こうの足跡は、既に風が砂をかけて消し去っていた。 (こんな馬鹿なこと、あるはずない。そう、きっと映画か何かの撮影のセットなんだ) こんな景色。 砂に埋もれた看板に書かれている文字は日本語。 これだけ大きな都市が無人で放置されている場所があるなんて話、聞いた事もない。 夢を見てるのだろうか。信じられるわけが無い。昨日まで普通に暮らしていた世界がこんな事になるなんて。 混乱した頭で何を考えても、一向にうまくまとまらなかった。 どんなに経っても夢は覚める気配はないし、照りつける太陽も埃っぽい風も、変わらず自分をなぶり続ける。 (きのう……?昨日……って、いつなんだろう。私、何してたんだろう) どうにか心を落ち着けて、今の自分の格好をかえりみる。 裸足の足。荒れた地を歩いていたせいだろう、傷だらけなのを自覚した途端、痛みに顔を歪める。 余裕のある服は、袖の少し短い上着と、上着と同素材のズボン。 少し濁ったような薄っぺらな無地の布を前で合わせた簡素な――入院着というものだろう。 およそ外を歩くには相応しくない格好だが、やっぱりどうしてそんな物を着てるのかは思い出せない。 病気か怪我でもしていたのだろうか。足以外に痛いところも具合の悪いところもないけれど。 あと、思い出せる事は……学校、街、家?その記憶のどれもが遠くかすれたようなモノでしかなくて、現実味が無い。 何もかもが今のこの破滅的な現状に繋がらなくて、歯痒かった。 (………まだ、混乱してるのかも……。どこかで落ち着いて、状況を整理しないと……) 重い頭を上げるけれど、その先には丸くくり貫かれたような、またはリンゴのように齧られたような巨大なビル。 「………」 アレらは、どうした"ああ"なったんだろう? どこぞからの大規模なテロ攻撃があったとしたって、通常の兵器であんな風になるものなんだろうか? 何か、人間の力ではどうしようもないモノに蹂躙されたような―― それ以上考えを進めると、自分の思考能力だけでは追いつかない域に達してしまいそうだった。 (とにかく、誰か他の人を見つけて、何がどうなってるのか聞いてみよう) 痛みを堪えて、また砂地に足を進める。 残酷に思えるまで澄み切った青い空を背に、廃墟と化した街に迷い込んでいく。 もとより来た道など分らないし、行く先の道も分らない。ただ、自分以外の存在を求めて。 けれど、行けども行けども、静寂の街はどこまでも広がっている。映画のセットどころじゃなかった。 (……のど、乾いたな……) 元々水分への欲求はあったのだが、この乾いた空気の中を延々彷徨っているせいで、それが深刻になってきた。 お腹もすいている。足も限界。日常生活でこんなに限界に近づいた事がなかったので、すっかり心も参ってしまった。 「もう……やだ……」 家へ帰りたい。でもそれが何処だかも、ここが何処だかも分らない。聞こうにも人がいない。何でこんなに誰もいないの。 「……つっ!」 建物の影になった方向へ曲がろうとしたところで、砂に埋もれていたガラス片かなにかを踏んでしまった。 「あうっ!」 激痛に身を捩ると、バランスを崩して転んでしまう。けれど倒れこんだ先にやっと見つけた。 穴の空いたオフィスビルや崩れかけた聖堂の影に、ひっそりと立ち並ぶ民家群。人が生活していそうな場所。 やった、助かった。疲れた心に希望が射し込み、逸る気持ちで痛みを無視して立ち上がると、入り口へと急ぐ。 でも、近づいてみて、その希望に翳が差すのを感じた。 割れた窓ガラスはそのまま。屋根も壁も、ビルの隙間から吹き込んでくる風に、今にも剥がれ飛んでいきそうだった。 干してある洗濯物……だったものは、乾き、汚れきってボロボロのまま靡いている。 家の中に明かりは無く、どこも同じように静まり返っている。 「……ごめん……ください」 半ば以上諦めが勝っていたが、それでも望みを捨てきれず、控えめに声を掛けて戸を開いた。 無人の部屋。 色の無い家具や、年月を経て放置され、変色した壁や小物。錆びたシンク。 生活のにおいがするものなど、そこにはただの一つとして無かった。 簡素な木のテーブルの上に、コップに入った水が底にほんのわずか、残っている。 手にとって飲んでみようとしたが、液体が唇につく所で、黴臭い悪臭が鼻を衝いたので思わず咽た。 取り落としたコップは砕け散り、腐った水は床に浸みこむ。 「けほっ……けほっ、……う、……うぅ」 止まらない咳に胸を掻き毟りながら蹲ると、テーブルの下に布人形が転がっているのに気付いた。 黒ずんだ人形の首はもげて、中の綿が見えていた。 「う……ぅうっ……」 何だかもう、限界で、訳が分らなくて、咳のせいで滲み出た涙が、喉が落ち着いても止まらなかった。 鳥も虫も、自分以外に声を立てるものは無く、もしかしたらもう、生きているモノがいないんじゃないか。 そんな予感さえした。そして本当にそうならば、途方もなく寂しく、恐ろしい事に思えた。 立ち上がる気力も完全に失くして、ただ溢れ出しそうになる恐怖や焦燥感を必死で押さえ込む事しか出来ない。 いつまでも風の音ばかりが続いていて、時々どこか遠くで、建物がゆっくり倒壊していく音が聞こえる。 しかし。 「…………!」 ふいに、耳に届いた微かな音に、意識が呼び起こされる。 ざっ、ざっ、という、規則的な音。自分が立てているものではない。 そう、足音だ。生物の、もしかしたら人間の。 (誰か……いる!?) そう思うやいなや、重い身体に鞭を打って外に飛び出す。 足音はそう遠くはない。この民家に影を落としているビルの向こうの方から聞こえる。 ゆっくりとした、重い足取り。何とか追いつこうと、痛む足を引き摺りつつ、走った。 そうして、やっとたどり着いてビルの影から見えた曲がり角の先、"それ"はいた。 (……!?) 全身の血が、一気に凍りつく。 自分の見たモノが信じられなくて、見開いた目が乾くまでに、その後姿を凝視した。 人じゃない。 人じゃなければ、動物でもない。 「………っ」 そのあまりの異様さに、息を呑む。 鬼の面のような頭部、大きな爬虫類のような体躯には二本の鋭い鉤爪のある足のみ。巨大な尾は棘に覆われている。 一目見て、体中が竦みあがる程の恐怖に駆られるには、相手は充分な姿をしていた。 あれに見つかっては駄目だ。本能がそう語っている。あれに見つかれば、私は死ぬ。 どうしてこの街が荒廃しているのか、どうして人がどこにもいないのか、解ったような気がする。 それらはきっと"あれ"が原因の一端なんだ。 化け物は此方には気付かず、幸いにも、逆の方向へ向かっている。 ざ、ざ、という重い足音が少しずつ遠ざかっていくのを、声を押し殺して耐えた。よくあんなものに出くわさずにいたものだ。 そうして、辛うじて姿が確認出来るまで離れた事を曲がり角の向こうにそっと確認して、息をつく。 ふと、自分にかぶさる影が濃くなっているのに気付いて、不審に思って空を見上げた。 「……!」 ギョロリとした大きな目玉が、此方を見下ろしていた。 丸い球体の身体に、巨大な一つ目の化け物が、音もなく頭上に浮いている。 目の下には大きな口があり、白い女の裸体のような部位が、飲み込まれる苦悶に叫ぶ天使のように見える。 「あ……あ…」 見つかってしまった。 恐怖が頂点に達し、がくがくと身体が震える。 後退りをしたのと同時に、その一つ目の化け物は凄まじい鳴き声を発した。 「い……い、いやああああぁぁ!!」 ガパ、と牙をむき出しにして突進してきたのを辛うじて避けながら、悲鳴を上げる。 それまで居た場所……ビルの一部を難なく齧りとって、一つ目の化け物はまた此方に向かってくる。 向こうから咆哮が上がったと思うと、離れていった先ほどの鬼面の化け物が走って戻ってくるのが見えた。 「あ、あ……あああああ!!」 血だらけの足を、震えて使い物にならない筋肉を無理やり動かして、逃げる。 それがどれほど虚しい抵抗なのかも解っていたけれど、とにかく恐くて、恐くてたまらなくて、無我夢中だった。 ドンッ!と、音がしたかと思うと、後ろから追いかけてきていると思っていた鬼面の化け物が目の前に降って来る。 物凄い跳躍力だった。 ひゅ、と、悲鳴にもならない息が喉を通り、絶望に駆られる暇も無く衝撃が襲ってくる。 その強靭な尻尾で払われて、倒壊しかけた家屋の中に突っ込んだ。 轟音が耳を襲い、全身を打って、痛みに呼吸がままならない。したたかに打った頭がくらくらとした。 「う……ぐ、う……がはっ!」 起き上がろうとした所に、また衝撃が降ってくる。仰向けの腹に、鉤爪が喰い込んだ。 眼前に、凶悪な鬼のような頭部が突きつけられる。グルグルと喉を鳴らす音と生臭い息が顔に降りかかってくる。 突き出た牙が頬にあたる。 (も、う……駄目……) 諦めて目をきつく閉じる直前、自分に喰らいつこうと大きく振りかぶった鬼面が見えた。 「いやああああ――――――!!」 断末魔のその瞬間。 重く肉を裂く音が、聞こえた。 腹の上の鉤爪が食い込む力がふっと弱くなり、直ぐ横で、どしゃっと巨体が崩れ落ちる気配が伝わってくる。 全身が心臓になってしまったみたいに、鼓動に合わせて身体が震え、荒い呼吸を繰り返す。 いつまでたっても喰い潰される衝撃に襲われない事を不思議に思って、恐る恐る目を開けてみるけれど、 視界が涙と埃でぐしゃぐしゃで、よく分らない。 「………ひと?」 声だ。私以外の人間の、発する。 「……何で、こんなとこにいる」 少し低くて、感情の無い。けれどそれは、確かに、言葉だ。私以外の誰かが、問うている。 切望していた他人の声に、相手が何者かも分らずに安心感が湧き上がって涙が出た。 ズリュ、と、重厚な金属質の何かが引き摺られるような音がする。 白い髪に浅黒い肌の男の人。灰色の瞳が警戒するように此方を鋭く見下ろしている。 背にあるのは大きな鋸のような武器……だろうか。べったりと付着している血は、あの化け物のものだろう。 顔を隠すようにフードを目深に被っていて、右腕には目を引く大きな赤い腕輪が嵌っていた。 「おい、答えろ」 こちらの気持ちとは裏腹に、声は冷たく迫るように響く。 とにかく何か答えないといけない、と涙を拭って視界をクリアにした瞬間、目に飛び込んできた光景に愕然とする。 「あぶな……!」 「なっ……おい!?」 思わず、身体が動いて、目の前の人物を突き飛ばしていた。 そうだった、自分を襲っていた怪物は鬼面の怪物一匹じゃない。 もう一匹、大きな口を開けて、男の人諸共こちらを飲み込もうとする単眼の怪物が見えた。 折角、助かったのに。迫る口を見ながら、咄嗟の自分には不釣り合いな勇敢さに後悔し、戦慄する。 「……クソッタレ、がぁッ!」 襲撃を避けて体勢を崩しかけたまま、男の人は驚くほどの身体能力を発揮し、足を軸に身体を回転させた勢いで 背の丈よりも大きな武器を振り上げる。 怪物の身体は豪快に切り裂かれ、振り切った勢いで壁に激突して動かなくなった。 やがてその亡骸は地に沈み込むように、黒い影に呑み込まれて消えていく。 目の前で男の人――よく見たら年も同じくらいの少年だった――が息を整えているのを、返り血を浴びたまま見ていた。 「……こちらソーマ。M地点にてターゲット二体と接触。いずれも撃破した」 "ソーマ"というのは、この少年の名前だろうか。 瓦礫の上に腰掛けて少年の声を耳に流し込みながら身を縮め、嗚咽を漏らす。 我に返った途端、恐怖や、安堵や、興奮といった抑えていた感情があふれ出して止まらなかった。 そんな此方に一切構う事無く、ソーマは通信端末らしきものを取り出して、どこかへ報告を続ける。 会うことは無かったけれど、やはりまだ他にも人はいたのだろうか。 「了解。……あ?………ああ、同地点で民間人……らしき人間を保護した」 多分、私の事を言っているんだろう。「民間人」という括りにされているという事は、彼らは別格なのだろうか。 先程の戦いぶりを思い出す限り、普通の人間じゃないような気はするけれど。 「………了解」 殊更低い声でそう返事をすると、遠慮のない動作で端末のボタンを切ると同時に、ソーマはチッと舌打ちをする。 そうして、不機嫌そうに少し離れた所の壁に背を預け、腕を組んだ。 以降、こちらの存在など無いもののように、黙って俯いている。 その間もずっと、私は泣き続けていた。 「おい……静かにしろ」 しばらくして掛けられた言葉には苛立ちが含まれていて、どうにかしなければと思いつつ、やっぱり止められない。 「……また襲われたいのか?」 「!」 だけれど、そう言われた瞬間、涙も血も凍りついた。 そうだ、声を立てていれば、先程の怪物みたいなのがまた寄ってくるかもしれない。 蘇ってきた恐怖と、無理やり涙を止めた反動で、今度は身体の震えが止まらなくなった。 「………」 そんな様子を、渋面でソーマは見ていたが、やがて溜息をつく。 「クソッタレが……よりにもよって、こういう時に適任な奴がいやがらねえ」 忌々しそうに舌打ちをすると、壁から背を離して此方を向く。 今度は何を怒られるのだろう、と、止まらない震えを必死で抑えようとしていると。 「……そら」 ぽつりと呟かれた言葉の意味が、分らない。 いよいよもって、ソーマの眉間には不機嫌さが募っているのだが。 「空を見ろ。そんで、動物の形をした雲を探すんだそうだ」 暫く首を傾げていたが、ともかくソーマの指示に従う他、自分に出来る事など無い。 おずおずと、空を見上げる。 日が傾きかけていて、快晴だった空には、少しだけ雲が浮かんでいた。 「………」 流れる雲を必死で目で追っていると、少しずつ、震えが治まってくる。何だかとても、安心した。 自分が一人じゃないというのもあるけれど、この少年が近くにいてくれる事を、とても心強く感じた。態度は恐いけど。 どんなに目を凝らしても、一向に都合よく動物の形をした雲は見つからない。 いつの間にかすっかり震えは収まって、ずっと上を向いていて痛くなってきた頭を戻して、ソーマを見た。 相変わらず、冷たく不機嫌そうな顔。 「……見つかったのか?」 何故か無収穫だと怒られそうな気がして、何とか答えになりそうな物が無いかと考えたけれど。 「綿菓子……」 「……動物じゃねーぞ」 呆れたような視線と声音で返された。 |
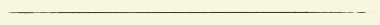
一話目から色々とぎりぎりだ
←back next→