
取り替え子
「ほら、な、もう傷がない」 きゅ、と、指先の唾液を拭き取る感触と、遠く近く響く声に、手放していた意識をは取り戻した。 傾いた日の色は、記憶のそれとあまり変わらない。ごく短い時間の気絶のようだった。 後頭部を座布団に預けた状態で、焦点を合わそうと瞬きをしていると。 「お。起きたか」 ぬう、と、影を背負った、白い髪に翡翠の目の男の顔が覗き込んできたので、心臓が飛び上がった。 「ぎゃあ!」 咄嗟に色気のない悲鳴を上げると、本能の命令に従うまま、男の顔を両手で押し退ける。 何となく、ぐき、という鈍く微かな音と感触が手の平を伝わって感じられたが、それに構う余裕もなかった。 飛び起きて、荒い息をついて暫らくしてから、漸くはっとする。 「…あ、うわっ、す、すみません!」 予想もしない攻撃に不意をつかれたのか、首をおさえて言葉も発せず痛みを耐えるギンコがそこにいた。 その横でしんらは圧倒されていたが、取り敢えずギンコに大丈夫?とでも言いたげな手が所在を欠いている。 「あの…つい…だって…」 無理も無い、と、言いたい。本能がそんな事を命令するのも納得の理由があった。 だって、意識を手放す前。 「だっ…て、わた、私…」 自分で言ってしまって、自分で思い出してしまって。 かあ、と一気に体温が上昇していく。 あまりの事に、その時感じたリアルな感触だなんて、一片たりとも思い出せないが、確かにギンコに指を、 ――――指、を。 (う、わああぁぁ) のぼせ上がった頭がパニックでどうにかなりそうだった。 しかも、何やら聞くだけなら如何わしい最後の台詞が、どんなに拒んでも鐘を鳴らすように頭の中を反芻する。 考えてみれば、他人の唾液を肌に感じるような事など、人生の中でどれ程あるものか。 将来の事を考えれば大した事でもないのだろうが、今までの日常からして免疫など微塵もない。 身体を起こしたのにも関わらず、そのまま頭を抱えて蹲ってしまったの背中を、しんらが優しくさすってくれる。 「平気?さん…、そんなに痛かった?」 彼はどうやら、今思い描いている不謹慎な事に対してではなく、身を切られた事にショックを受けていると思っているようだ。 いいや、何というか、もう。 痛いなんてもんじゃなくて。(心臓は痛いが) 熱の昇る顔を隠しながら、とにかく心中以外は大丈夫です、と首をふる。 そう?と、僅かに名残をのこしながら、しんらが安堵の息を漏らした。 「…悪かったな」 いまだ違和感の残る首をさすりながら、ギンコはふてぶてしい声で詫びてみせた。 言葉の内容とはうらはらに、何で自分がこんな目に、という腑に落ちない感情がありありと見て取れる。 申し訳ないとも思うのだが、同時に、こんな事までやってのけて平然としている様子に腹が立たない事もない。 とはいえ、先程の時と同じく、今回も彼は純粋に調査の一環として行動に出ただけなのだろう。 それがどういう形になるのかはには全く予想がつかないし文句も言えない。 ギンコに非はない。あるとすれば、やっぱり過剰に反応してしまっている自分だ。 「いえ、こちらの方こそ、本当にすみません…。あんまり人と接触する機会のない人生でして……つい」 どんな孤独な人生だよその言い方は、と、心のどこかからツッコミが入るが、あながち間違ってはいない。 「ほお。聞くからして、稀な境遇だと思っていたが、やはり育った環境も常人とは異なる、か?」 ああ、しまった。しごく真面目に受け取られてしまった。 「あ……その、気にしないで下さい。生活様式が違う以外は至って普通なんです、普通…」 ギンコが眉を寄せて訝しんでいる様子を見て、余計なことは考えない、言わないようにしようと誓った。 気を落ち着けて、謝罪を口にしてから、改めて自分の手の先がどうなっているのかを窺う。 しかし。 「…あれ?」 流れていた血も、唾液も拭き取られたそこには、常と同じ傷の無いつるりとした指先しかなかった。 これは一体、どうした事か。 ギンコが自分に何かを施したのだろうか?手品をやったなんて事もあるまいに。 気のせいとするには、しんらやギンコの言動がそれを許さない。 「どうして…?」 独り言のように呟いたそれだが、戸惑いを抑えきれずにギンコを見上げた事で、それは問い掛けとなった。 感情の読み取りにくい緑の目が伏せられ、口から溜息が漏れる。 「…アンタ自身に、"この状態″に対する心当たりはないのか」 ついた傷がすぐに治る、なんていう事を、生まれてから今まで気付かないなどという事は、さすがにない。 にしてみても、自分がそんな特異な体質を持っていたなんて記憶は、どこにもなく。 今のこの状態があまりにも信じられなくて、むしろ自分には関係ない事のように思えてしまって、「知らない」と首をふる。 そうすると、ギンコは先の調査で見出した可能性を、答えにするか否かと思案しだした。 黙って考え込む彼を、そこまで頭を悩ませる事があるのだろうかと、不安に見守る。 自分はどうなってしまったのだろう、漠然と、大丈夫なのだろうか。 横のしんらも同じような顔をして、黙々と沈黙を続けるギンコを待っていた。 やがて。 「…ほんとうに」 最終確認、とでも言いたげに、ぽつりと言葉が投げかけられる。 「何もなかったのか?……よく、思い出してみろ。何でもいい。何か奇妙な事はなかったか」 よほど彼自身、導き出た結論に納得がいかないのか、信じられないのか。 念をおすような問いに、いよいよ自分の身体にとんでもない事が起こっているのかもしれない、と恐ろしくなった。 もう一度、少ない記憶をかき集めてみたけれど、自分にとってはどれも奇妙で、ここでの日常との区別がつかない。 あと、言ってない事があるとすれば、思い当たるものが無くもない。 もう、恥ずかしいから思い出したくないだのと言っている場合ではないだろう、と、腹を決める。 「夢で…」 闇の中の、朧ろげな、光景。 現実とは無縁の、あのすがた。 戸惑いがちに話し出したの話を、聞き漏らすまいとギンコが僅かに身を乗り出してくる。 動揺を隠しながら、根拠のない話を口にするのに抵抗する理性を抑え付けた。 蟲に関してはまだ解らないが、どんな形の蟲がどういった形で人と関わりあってくるのかは本当に様々らしい。 「夢」と口にしても、ギンコの興味は逸れなかった。 「…ものすごく、大きな光の河にいて……でも、流れているのは、水じゃなくて」 自分の見たものが、あまりに御伽噺めいているので、馬鹿にされやしないかとヒヤヒヤする。 しかし、窺うギンコの顔には、不審どころか確信めいた、どことなく苦味のある表情が浮かんだ。 「光脈だ」 「こうみゃく?」 まだ夢の一部を話し出して間もないというのに、断定したギンコの言葉に、不思議そうにしんらが声を上げる。 も、まさか曖昧な記憶がはっきりとした正体として返ってくるとは思いもよらず、説明を待った。 「しんらには、さっき言ったな。……全ての、生命の源」 とん、と、心の臓のある部分をさす親指を見て、しんらはうん、と頷いた。 「それらは、光酒という。光酒が集まり、大河を成し、どことは言えない場所を流れている。 蟲というのはここに一番近く、人間は一番遠い」 淡々と、ギンコは言葉を紡ぐが、は解るようでいて解らないその話を、必死になって頭の中で追った。 何と言おうか、考えるよりも、感じるような話だ。 全ての生命の源。 “いのち”という言葉でひとくくりにされた領域。 植物も、動物も、人間も、全ての区切りを取っ払った、そういう次元。 「しかし稀に、人はこの光の河に対峙してしまう時がある。元の素養を除いては、大概が蟲と関わってしまった影響だ。 そりゃア、綺麗なモンだが、人が人であるのなら毒になる。…見てはいけない。触れちゃならねえ」 あまりにも神聖なもの。いいや、違う。善も悪もない。 神と呼ぶほど傲慢で偉大な存在ではないが、等しく尊ぶべきものに、人間という生き物は相反する。 しかし、そんな大層なものとは露知らず。 「え……え、あの、……つかぬ事を聞きますけれど、見て、触れちゃった場合は…?」 いけない、と言われても、自分は既に。 ギンコは、やはりその類か、と言いたげに息を吐き出すと、先程よりも重々しげに語る口を続けた。 「あちら側――……つまり、蟲達の世界に引き込まれる。もう、人間には戻れない」 「そ……そんな…」 ああ、だからあの時ギンコは必死になって止めていてくれたのだろう。 そうとも知らず、私は何て事を。人間には戻れない、なんて。 そんな自覚は無くても、経てしまった事実は、その結果の体の変化は、逃げる事を許さない。 「ね、ねえ、ギンコ。それじゃあ……ここに今いるさんは、人間でないって事?」 ショックが大きくて聞くのが恐かったその疑問を、代わりにしんらが発してくれた。 少年の、心配と不安が交じり合ったような視線を受けて、緑の片目が暫し伏せられる。 またも考え込むように片手に顎を乗せ、ふう、と煙草の煙が深く吐き出された。 「それが、どーもなァ……。何といったらいいか、意味が解らん」 もっさりと、眉間に皺を寄せたギンコが、いやにきっぱりと曖昧な答えを出してみせた。 「………はァ…?」 それが自分の声だったのか、しんらの声だったのかは解らない。 いやいや、おい。意味が解らないのはこちらの方ですよ。 「あー……で、話が切れちまったが、その光脈を前に、お前さん、どうしたって? それ如何によって、答えがでるやもしれん」 胡散臭そうな、疑るような二人の視線を受けながら、ギンコは冷や汗を後ろへ隠して呻くように言う。 まあ確かに、詳細も解らないのに結論を出すのは早計か、とは息をついた。 そう、確か、自分はその光脈を前にして。 前に…して。たしか。 「ええと、流されました」 「………」 取り敢えず、恥になりそうな部分を省いていくと、そうなった。 間違ってはいない事実をありのままに伝えると、煙草を銜えたままの口が半開きのまま、表情が固まった。 「……………………どこまで」 あまりの呆れっぷりがそうさせたのか、的の外れた問いを返してきてしまった彼に、居心地悪く答える。 「…………さ…さぁ」 どこって。地名も何も、目印すら何もないあの闇の空間の、どこを指せと。 それ以前に、意識を失って、最後はどうなったかも解らないし。 「……………ハァ」 小さな溜息が聞こえた。 何てこった、と、それ以降片手で眉間を押さえながら黙るギンコに、何とも声を掛け辛い。 ちらちらと、同じような状態のしんらとアイコンタクトを取りながら、今唯一の頼りである蟲師の復活を待った。 やがて。 「……あ」 何かが繋がったような感情を含んだ翡翠の片瞳が、此方を向く。 「もしかして、アレか。アンタ、あの対岸で年甲斐なく大泣きしてた…」 「わ、わああぁあ!!」 顔を上げて語り始めるのかと思いきや、覚えはあれど一番思い出したくないエピソードを口にしだしたギンコを 思わず悲鳴で制した。 「……………」 「ど、どうしたの、さん!?」 それはもう、しんらも吃驚した様子で身を引いている。 「……あ、な、そ……お、覚え…!?」 呆れ顔に汗を伝わらせているギンコに指をつきつけながら、身を焦がす程の恥に震える声で確認をとると。 しぶしぶ、と、白髪の頭が縦に揺れた。 「いや…あんまり色々と突拍子なかったもんだし、顔とかよく見てなかったから…」 「…………そ、そ、」 そうですか、とマトモに言えないに対して、もう一度落ち着いて頷く。 その、衝撃的な事象は確かに覚えている、と、ギンコはあの夢を肯定した。 いいや、それは夢などではなかった。 「アンタを不可解な事に引き込んだ原因になるとしたら、それだな。光脈の流れに呑まれた人間がどうなるかなんて 予想もつかない。人としての形を、保っていられる事も信じられないくらいだ」 肌のあわ立つような事実を言われ、今更ながらに自分がここにいられる事にひどく安堵した。けれども。 「……それを思うと、いまの“この状態”も、ひとつの形としては有り得なくもない」 人にとって毒となる物に触れた自分が、無傷だなんて思えない。 長らくの憶測、予測、推察、曖昧なそれらの結論がやっと出た、と言わんばかりに、ギンコの顔はすっきりとしている。 「どういう事なんですか?……私は、もう、人間じゃ……」 限りなく低い、人間である事への可能性を問うに、厳かに、かみしめるように、ギンコはゆっくり頷いた。 それは肯定なのか、否定なのか。 やがて焦れったい、けれどもほんの一瞬の間をおいて、宣告が下る。 「……人間だ。、あんたは…――――光酒で出来た、人間だ」 |
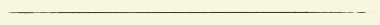
光酒おいしそうです
←back next→